「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.23 (2017.11.25発行)
◆前回紹介した世界システム論では、ヘゲモニー国家の例は3つだけでした。すなわち、17世紀中ごろのオランダ、19世紀中ごろのイギリス、第二次世界大戦後からベトナム戦争前までのアメリカの3つです。今回はイギリスのとても有名な小説を取り上げますが、この本の作者はヘゲモニー国家になる前のイギリスに生きた人物であることを念頭に紹介することにします。
■ダニエル・デフォー(1719)『ロビンソン・クルーソー』[増田義郎(2007/2010)、中公文庫]
ロビンソン・クルーソーって無人島で一人でサバイバルした話、という程度の認識しかなかったのですが、今年の夏になって初めて読んで、案外奥が深いと思いました。読んでいるときは少々かったるく、まあこんなものか、と思っていましたが、訳者・増田義郎の解説を読んでびっくり、蒙を啓かれる思いがしました。この小説は単に、絶海の孤島で自助努力した男の物語、あるいは孤独のうちに信仰に芽生えた男の物語にとどまるものではなかった!実はこの小説は、当時の時代背景がかなり正確に描かれていて、それを踏まえるとまた違ったふうに読めてくるのです。極端に言えば、歴史的文脈にこの作品を置かなければ、作者が意図したことを読み違える可能性さえある、といっていいかもしれません。
〇『エミール』にみるロビンソン・クルーソー
時代背景の前に、これまでの一般的なロビンソン・クルーソー像を見ておきましょう。ここで参照したいのがジャン・ジャック・ルソーの教育論、『エミール』(1762、今野一雄訳・岩波文庫)です。この本はエミールという生徒を、彼の成長段階に従ってその家庭教師がいかに教育するか述べたもので、有名な社会契約論に匹敵するルソーの主著として重要です。その第三編でルソーは「わたしは書物はきらいだ。書物は知りもしないことについて語ることを教えるだけだ」と言いながらも、次のように述べています:「わたしたちにはどうしても書物が必要だというなら、私の考えでは、自然教育のもっともよくできた概説を提供する一巻の書物が存在する」;「いったい、そのすばらしい本とはどんな本なのか。アリストテレスか、プリニウスか、ビュフォンか。いや、ロビンソン・クルーソーだ」。つまり、ルソーは子供に読ませる本の具体例として唯一このロビンソン・クルーソーを挙げているんですね。実はこの教育論・エミールのおかげでロビンソン・クルーソーは子供たちに読まれる(読ませる)ようになったのではないか、という気もしますがどうなのでしょう。
ルソーには「主人公の行動を検討して、なにか忘れてはいないか、もっとうまくやることはできないものかしらべ、かれの過失に慎重な注意をはらい、それを教訓にして、同じようなばあいに自分はそういう過失をしないようにする、といったふうになってもらいたい」という思いがあったようです。彼によると、「この物語は、あらゆるがらくたをとりのけると、その島の近くでロビンソンの遭難にはじまり、かれを島から救い出しにきた船の到着で終わって」おり、「ロビンソン・クルーソーは、かれの島にあって、ひとりで、仲間の助けをかりることなく、どんな技術の道具ももたず、しかも生きながらえ、自分の身をまもっていくことができ、さらに、快適な生活といえるようなものさえ手にいれることができた」そうです。ここにぼくは一般的なロビンソン・クルーソー像が見事に示されているように思います。
〇実はおもしろい「がらくた」
ルソーはクルーソーが無人島に流れ着いてそこから脱出するまでが小説の主体でそのほかは「がらくた」だとみなしていたようですが、そのかわいそうな「がらくた」について述べておきます。実は小説には無人島に流れ着く以前のクルーソーの生い立ちについても書かれていて、これはこれで波乱万丈です。(個人的には無人島生活よりこちらの方が読んでいて楽しめました。)また、無人島を脱して故国イギリスにもどった後も多少の冒険があり、デフォーは続編『ロビンソン・クルーソーの新しい冒険』(こちらは岩波文庫で読める)および『ロビンソン・クルーソーの反省』も出しています。ただし続編は冗長で魅力に欠けるそうで、ぼくは読んでいません。
続編はともかく、無人島につくまでの物語を聞いてください。というのも時代背景を考えるのには無人島生活よりもむしろこちらが重要だからです。クルーソーは1632/9/30にイギリス・ヨーク市の裕福な家の三男として生まれました。クルーソーは「なにがなんでも外国に行きたい気持ち」で、中間階級が人間としての最上の身分だと説く父の戒めを振り払って1651/9/1にロンドン行きの船に乗ります。ところが嵐に遭い、早々に後悔する羽目になるのですが、失敗して帰郷することの羞恥心と、成功して金持になりたいという野望から、アフリカ海岸行きの船に乗ります。最初の航海で40ポンドの元手で300ポンド得られたことに気を良くして2回目の航海に臨みますが、モロッコ・サレのイスラムの海賊に襲われ、奴隷の身になり下がります。2年間奴隷の身でしたが、チャンスをいかして小舟で脱走し、運よくブラジル行きのポルトガル船に発見されて救われました。寛大な船長の世話になり、ブラジルで農園と砂糖工場の所有者に紹介されて農業経営者を志します。食料に加えてタバコやサトウキビの生産に乗り出し、軌道に乗ってきましたが、人手が不足していました。農園経営を始めて4年目、他の農園主と相談して、黒人奴隷の密貿易に乗り出すことにし、クルーソーは1659/9/1にアフリカ行きの船に乗ります。ところが運悪く嵐に襲われ、9/30、ただ一人無人島にたどり着き、生き延びたのです。
〇原著のタイトルページ
次に見てもらいたいのが原著のタイトルページです。こちらは武田将明訳(河出文庫)から引用します:「ヨーク出身の船乗り、ロビンソン・クルーソーの人生と不思議で驚くべき冒険/アメリカ大陸の沖合、巨大なオリノコ川の河口に近い無人の島にたった一人で、二十と八年生活した記録/船が難破して岸に打ち上げられたが、彼のほか全員が命を落とした。/および/海賊から彼がついに救われるに至った不思議ないきさつの記述/本人著/(以下略)」
どうでしょう、けっこう話の筋が書かれていてネタバレになってしまっている気もしますね。ただ、ここで注目したいのはクルーソーの漂着した島について「巨大なオリノコ川の河口に近い無人の島」とかなり具体的に書いてあることと、「本人著」となっているように作者ダニエル・デフォーの名前は一切出さずにロビンソン・クルーソー本人が書いたかのごとく装っていることです。
無人島があるのはオリノコ川河口付近ですが、このオリノコ川というのは南アメリカ大陸の赤道よりさらに北にあって、東西に大西洋へと流れています。つまり、無人島と聞くと知られざる絶海の孤島を想像しますが、実は南アメリカ大陸の近くにある島だったんですね、ちょっとロマンに欠けるような……。しかしこれにはそれなりの理由があったらしく、このあたりは当時スペイン、ポルトガルの勢力が及ばないところで、しかもその北にあるいくつかの島嶼と南のスリナムではイギリス人が植民活動をしていたんですね。だから当時のイギリス人の関心はオリノコ川の水域一帯に集まっていた、と、こういう背景があったわけです。
本人著、として本書が出たというのも重要です。今の読者はダニエル・デフォーの小説として読みますが、当時はロビンソン・クルーソーという数奇な運命をたどった男の自叙伝として出版されたのですから。実は当時は旅行記、航海記が大ブームだったようで、1500年から1700年までイギリスで刊行された航海記、旅行記は500以上にのぼるそうです。この作品がいつごろからデフォー作として認知されるようになったのかぼくはわからないのですが、当初はこうした航海記ものの一つとして世に出されたのではないでしょうか。だとすると求められるのはその時代に密着したリアリティーであり、ここにデフォーは注意を払ったはずです。そしてそれを読み解くには多少の時代背景の知識が必要なのも当然でしょう。
〇イギリスの新世界への進出
訳者・増田義郎の時代背景を踏まえた解説が大変に興味深かったので少し紹介します。一言で言えば、ロビンソン・クルーソーが外国に行って成功して金持になりたいと野望を抱いていたのは当時としてはさして珍しいことでもなく、むしろこの時代の一つの典型像であり、そこから数奇な運命を辿るところにおもしろさがある、というのが増田さんの結論です。
ロビンソン・クルーソーの舞台は17世紀後半ですが、この時代はイギリスにとっての転換期でした。16世紀のイギリスは言ってみれば海賊大国で、国王や貴族らの認可状を受けた海賊(=掠奪行為を行う者)がイギリスの経済発展に最大の貢献をしていました。とくに標的になったのはスペインで、アメリカ大陸でスペイン人が得た豊富な産物が本土に向かって大西洋を渡るときがとくに狙われたんだとか。スペインから掠奪した量はハンパではなかったらしく、これが後世の産業革命への重要なステップになったと言えるかもしれません。一方17世紀に入ると、イギリス人はカリブ海の島々を占拠しはじめます。そうすると植民事業を始め、貿易に乗り出すようになります。
この海賊行為・掠奪から植民・貿易への移行期、これがクルーソーが生きた時代でした。掠奪よりも砂糖のプランテーションを経営するか、奴隷貿易をする、つまり三角貿易に携わるほうがはるかにもうかる時代になってきたのですね。すでに説明したように、クルーソーは、プランテーション経営を始め、奴隷の密貿易を企てました。この調子でもし彼が嵐に遭わず奴隷の密貿易に成功していたら、サトウキビのプランテーション経営に一層邁進し、莫大な財を築いていたことでしょう。重要なことは、これは当時リアルに起こっていたことだ、ということです。だからこそ訳者は、「ロビンソン・クルーソーは、正常なイギリスのブルジョア社会から逸脱した流れ者のアドヴェンチャラーではなく、むしろ一七世紀当時のイギリスの海外商業活動の生み出したもっとも典型的な型のひとつを代表している」と言います。
クルーソーが無人島につくまでは、ルソーが「がらくた」と呼んだ部分ですが、設定としては当時の読者のとってリアルな話だったのでしょう。この部分があるからこそ、無人島に生きる羽目になったことが典型からの逸脱としておもしろみを持つという訳者の解説に納得しました。しかしそれがリアルなものとして読まれなくなったとき、より普遍的おもしろさをもつテーマ――自分一人ですべてをこなして生き抜くということ――を扱った無人島生活の部分が主に読まれるようになったのではないでしょうか。エミールの出版はロビンソン・クルーソーより40年以上後のことで、もうこのときには時代背景と切り離されて読まれるようになったのかもしれません。
最後に、ぼくは時代背景と切り離して読むことを決して否定しているわけではないことを断っておきます。そうした背景知識なしに素直にテキストを読み込むことも大切ですし、この本はそうする価値のある本だと思います。むしろそうしたいと思う人には以上の話は妨げになるのでぼくは謝ります。今回メインで紹介した増田訳は時代背景の解説が素晴らしかったのですが、研究のための本ではなく、生きる糧として読まれることを目指した武田訳(河出文庫)もあり、こちらもパラパラ見たところ読みやすいです。(そのほか、岩波文庫、集英社文庫、新潮文庫などからも出ているようです。)
◆あとがき
いつもより遅れての発行になりました。本当はあと一週間早く発行するつもりだったのですが、腹の調子が悪くて寝込んでいたり、(本業の)建築設計課題に追われて手がつきませんでした。とくに腹を壊して40度超の熱が出たのはこたえました。医者に行くと感染性胃腸炎だと言われ、抗生物質その他を処方されましたが、ぼくはもともと抗生物質の過剰使用に問題意識を持っていたので、買っておきながら抗生物質だけは服用しませんでした。本当はその場で医者に飲みたくない意思を告げればよかったのですが、40度の熱は口を開くのもおっくうでついそのままにしてしまったことを反省しています。
ぼくが抗生物質に問題意識を持ちはじめたのは最近はやり(?)の微生物本を読んでからです。ヒトの体表および体内には想像を絶する数の微生物が棲んでいて、これらの微生物由来の細胞数は100兆を超えるといいます。ヒト自身の細胞数は37.2兆という数字があるので(通説の60兆は古いらしい)、微生物の方が断然多いです。重さにすると1キロを超えるそうなので、体重を軽めに申告したい人は微生物の分をアバウトに引くのもアリかも。とはいえ、体内の常在菌はヒトの免疫系にきわめて重要な役割を果たしているらしく、彼らなしには早々に感染症に負けて死ぬだろうと言われています。この体内の常在菌の多様性を確保することが重要で、一方抗生物質はこの常在菌の生態系を攪乱し多様性を減少させると言います……ダメだ!このまま書いているとまた長くなりそうです!重要なテーマなのでまたいつか改めて取り上げようと思います。結論はカンタン、抗生物質は本当に必要な時だけ使用すること、以上。
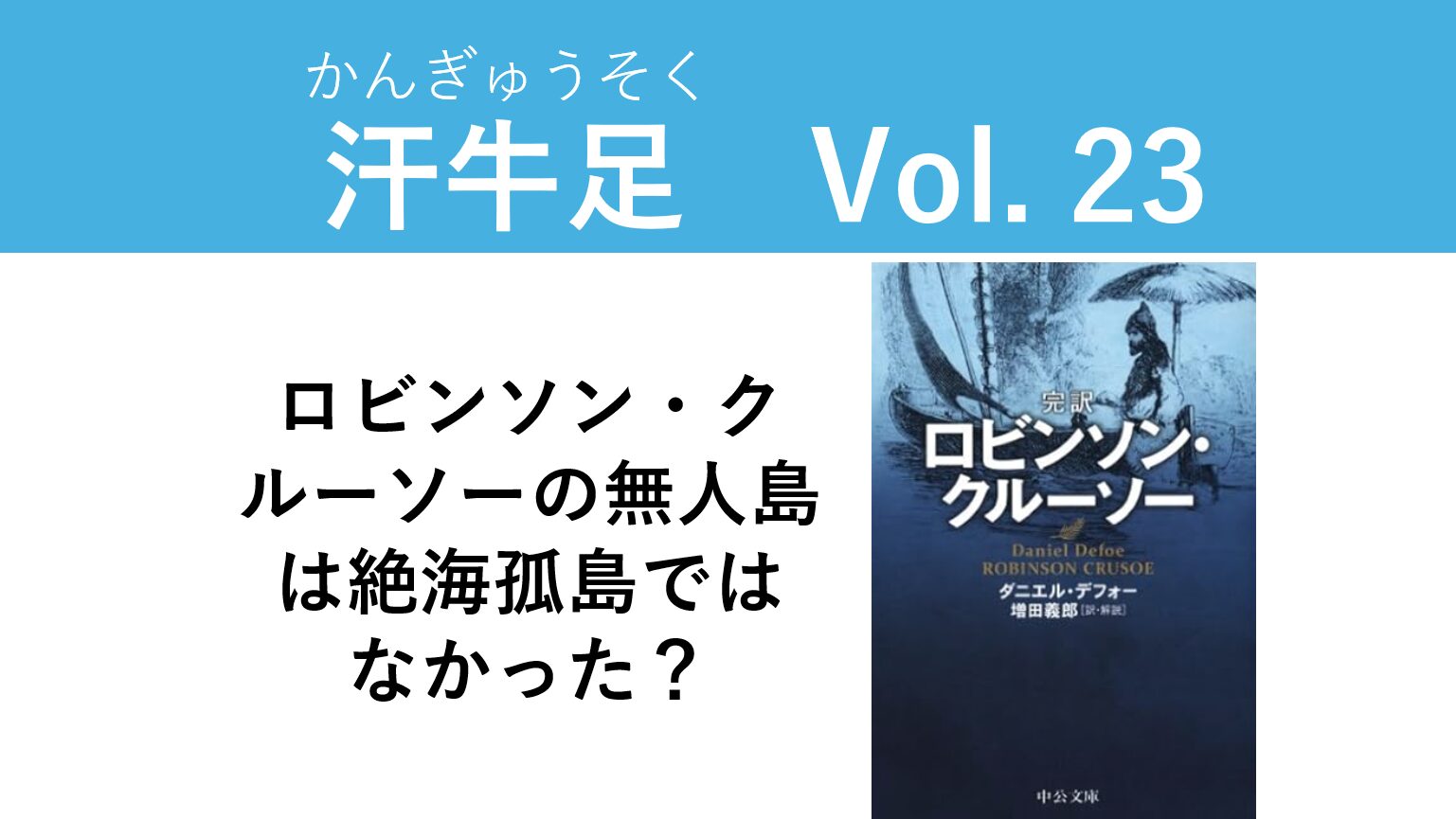


コメント