「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.25 (2018.1.13発行)
◆あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
年は改まりましたが、内容は引き続きガリヴァー旅行記についてです。前回はフウイヌムとヤフーの問題を取り上げましたが、今回は植民地問題に関わる話です。
■ジョナサン・スウィフト(1726)『ガリヴァー旅行記』[平井正穂訳(1980)岩波文庫]
前々回に、『ロビンソン・クルーソー』は掠奪から植民・貿易へと転換するイギリス社会という時代背景と密接に関わったリアルな本だったと書きました。それだけに主人公クルーソーはまさにこの時代の申し子であって、プランテーション経営にも乗り出しますし、奴隷の密貿易も計画していたわけです。ところがガリヴァーは違います。そもそもガリヴァーはあくまで船医として船に乗っていたので、彼は直接貿易に関わっていたわけではないのです。その上、第4篇の最終章でフウイヌムに感化されたガリヴァーは激しい植民地批判を展開しています。この箇所はとくに興味深いので、長くなりますが引用します:
「たとえば、海賊の一隊が暴風雨にあって海上をあてどなく漂流していたとする。やがて一人の少年がトップマストの上から陸地を発見する。よし、掠奪だ、とばかり一同上陸する。ところがそこに現れたのが罪のない土着民たちで、至れり尽せりの歓待をしてくれる。海賊たちの方はその土地に勝手に新しい名前をつけ、国王の名代として正式な領有権を宣言し、その証拠に朽ち果てた板切れ一枚か石ころ一つをおったてる。そして、なんと土着民を二、三千人殺し、なおその上見本として一組の男女を力づくで引っ捉えて帰国し、今までの犯罪の釈免状を手に入れる。ざっとこんな具合にして、まさに「神権」によってえられた新領土が確立されてゆくというわけだ。早速機会あり次第、艦船が派遣され、土着民たちは追い払われるか皆殺しにされる。彼らの王様たちは、金の隠し場所の白状を迫られ、あげくの果ては拷問にかけられる。どんな非人間的で貪欲な振舞いでもすべて公然と許される。大地は、原住民の流す血で一面に染まる。かかる敬虔な遠征に参加して、ひたすら虐殺に専念する言語道断な一隊、これこそ、偶像を崇拝する野蛮な土着民たちを改宗させ、文明に浴させるために派遣された「現代の移住民」の偽らざる姿なのだ」。
[pp.421-422]
「海賊の一隊」から「現代の移住民」への流れになっていることに注目してください。前々回に「海賊行為・掠奪から植民・貿易への移行期、これがクルーソーが生きた時代」と述べましたが、それがまさにここにも当てはまっていると思いませんか。つまりガリヴァーの描くこの海賊から移住民への流れはほかならぬ母国イギリスの姿であると思うのです。実際に、例えばカリブ海のセント・キッツ島では、もともと採集狩猟民のカリブ族が住んでいましたが、トマス・ウォーナーというイギリス人が本格的植民を計画し、先住民の大部分を虐殺したといいます。(増田義郎(1989)『略奪の海カリブ』岩波新書、pp.104-105)ここまで読むとガリヴァーとクルーソーの対照は一目瞭然です。クルーソーがまさに移住民そのものだったの対して、ガリヴァーはフウイヌムの影響を受けてその徹底的批判者となったのですから。つまり、彼はイギリスの対外膨張に関してクルーソーと180度ちがう見解を持っているといっていいくらいに思えてきますよね。
ところが、この引用箇所の直後の一文がなんとも絶妙すぎます!:
「しかし、いま言ったことがけっしてイギリス国民のことを指しているものでないことは、ここで断っておきたい」。
いやいや、これはあからさまなウソでしょう!しかもその後に、イギリスの植民地経営は「実に賢明で用意周到で公正」とまで書いていますが、ぼくにはどうしても皮肉にしか見えません。しかし文面上はガリヴァーは肯定的評価を下しているのですから、結局のところ、イギリスの対外膨張に関してはクルーソーと180度+180度“ちがう見解”を持っていたのかも。それにしても、スウィフトはなぜ人間=ヤフーを尽く嫌悪するガリヴァーに「わが国民は、植民地問題に関しては全世界の模範」とまで言わしめたのでしょうか。あの人間嫌いのガリヴァーがイギリス国民を讃えるのは違和感がありすぎます。
ここで立ち返ってみたいのが、以前vol.21で紹介したラス・カサスの『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(1552)です。少し復習すると、彼はスペイン人による先住民インディオに対する征服戦争や戦争後の強制労働の残酷さを生々しく描き、現状の改善を訴えたのですが、それは後に各国語に翻訳されてスペイン人は残酷であるというイメージが広がるという彼が意図せざる事態につながり、反スペイン感情を煽るために政治的に利用される、ということまで起きたのでした。ガリヴァー旅行記はラス・カサスの本が出てから150年ほど後の本なので、スウィフトが『簡潔な報告』の英訳を読み、それがラス・カサスの意図に反して悪用されていることも知っていたとしてもおかしくありません。こうしたことをふまえると、ガリヴァーが植民地批判をしながら、イギリスの植民地経営を称賛したのは、イギリスの対外膨張を皮肉りながらも、ラス・カサスと同じ轍を踏まないためのレトリックだったのではないか、とさえ思えてくるのです。あるいは、かつてのスペイン人と大差ないことをやっておきながら、「スペイン人の残忍さと貪欲さ」を非難するイギリス人を強烈に皮肉ったのではないかと思えます。
実は、その「スペイン人の残忍さと貪欲さ」を非難する同時代のイギリス人の例として、デフォーの描いたロビンソン・クルーソーを挙げることができます。というのもクルーソーはこう述べているからです:
「住民たちは、その習慣において偶像崇拝を行う蛮人であり、人間をじぶんたちの偶像に捧げる、血なまぐさい野蛮な儀式をおこなっていた。その彼らも、スペイン人に対しては、なんの罪もない人たちだった。この人たちを根こそぎにしたことは、当時のスペイン人みずからによってすら、最大の嫌悪と憎悪の感情をもって語られ[←ラス・カサスのことか?]、いわんやヨーロッパのその他のキリスト教国民からは、神にも人にも申し開きの立たない虐殺、血なまぐさく自然に反した残虐行為と受け取られているのである。そして、スペイン人の名は、人間的でキリスト教的なあわれみのこころを持つすべての国民にとって、おそるべき、身の毛もよだつようなものと考えられ、スペイン王国とは、寛大な心情のしるしとされる優しさの原理、哀れな者たちに対して共通に抱く同情には縁のない種族によって生み出されたものとして、とくに有名だった」。[増田義郎訳、中公文庫、p.248]
あからさまにスペインに対する否定的見解が披歴されていますが、ぼくはこの箇所は誇張だとは思いません。いかにも当時の一般人としてのロビンソン・クルーソーに相応しい意見でしょう。しかしスウィフトに言わせればロビンソンもスペイン人と同じ穴の狢だったと思うのです。実際、ロビンソンは脱出までに島に到来した何人の「蛮人」を銃殺したことでしょう!そしてその背後に垣間見える白人としての優越意識!(ぼくがどうしてもロビンソンに共感できない理由がここにあります。)
クルーソーはスペイン人の残虐さを非難していますが、やっていることは大差ないのではないか。そして当時のイギリス人も大方ロビンソンと同様で、スペイン人の残虐行為には強い嫌悪感を持つが自国民の残虐さには考えが及ばなかった。そこをスウィフトは皮肉ったのではないかと思うのです。
また、スウィフトがイギリス人の植民地批判をガリヴァーに述べさせた理由を考える上で、彼の生い立ちと複雑な立ち位置が参考になると思うので、最後にそのことについて触れておきます。
ジョナサン・スウィフトが生まれたのはアイルランドのダブリンです。アイルランドといえば島の北側は「北アイルランド」として(少なくとも現時点では)イギリスに属しているので、アイルランド≒イギリスと思っている人もいるかもしれません。いや、ぼく自身最近までなんとなくそう思っていたのですが、イギリス史・アイルランド史を少しかじって認識を改めました。(以下、波多野祐造(1994)『物語 アイルランドの歴史』(中公新書)を参考にしています。)アイルランドとは一言で言えば「イギリス最古の植民地」であり、イングランドを中心とするグレートブリテン島に搾取されてきた歴史を持ちます。アイルランドがイングランド王ヘンリー2世の支配下に置かれたのは1171年ですが、イギリスの実質的な支配が強まったのは16世紀の(あのトマス・モアを処刑し、イギリス国教会を樹立した)ヘンリー8世の時代からです。固有の文化を有していたアイルランドはイギリス化が進行し、イギリス人のアイルランド入植と大規模なアイルランド人の国外移住によりアイルランドの様相は一変します。また、とくに1649年のピューリタン革命の後、革命の指導者クロムウェルによるアイルランドの武力平定がなされたことは特筆に値するでしょう。その徹底的で無差別的な殺戮はのちのアメリカ進出と原住民の虐殺を想起させられます。ついでに言えば、実は17世紀にアメリカ大陸の植民に携わった人々の多くは、その以前にアイルランドの植民に参加しているので、アイルランドへの入植は17世紀のアメリカ進出の前段階としての意味を持つ、との議論もあります。(増田義郎(1989)『略奪の海カリブ』岩波新書、p.96)また、アイルランドはカトリック教国だったのに対し、イギリスはイギリス国教会というプロテスタントの一派の国です。クロムウェル以後は地主・支配階級がプロテスタントにすげかえられ、カトリックは被支配階層としてさまざまな差別を受けることになります。スウィフトが生まれたのはこうしたカトリックが多数派ながら少数派のプロテスタントに社会的にも経済的にも支配されたアイルランドだったのです。
アイルランド生まれとはいえ、スウィフトの両親はイングランド人でした。したがって彼はアイルランドにおいて少数派だが支配階級にあるプロテスタントに属していたとみなせるでしょう。生まれて間もなく孤児同然の状況に置かれて伯父の家で育てられたそうで、彼がイングランドに渡ったのはダブリン大学を出てからでした。それでもアイルランドへの帰属意識はあまりなかったようで、かといってイングランド育ちではないことは確かでした。アイルランドで生まれ育ったことはイングランドでの彼の社会的地位を低めたのではないかと想像できますね。政界への野心もあったようですが、結局46歳でダブリンの聖パトリック教会の首席司祭になりました。つまり、カトリックが多数のアイルランドにおいて、プロテスタント教会の司祭になったわけですね。イギリス本国で成功することはできずに、生まれ育った土地に帰ってきたというところでしょうか。
彼が自分の境遇をどのように考えていたのか分かりませんが、ぼくには彼が故郷のない人のように映ります。でもイングランドとアイルランドの双方に深く結びついていることも確かです。その分、両者の支配・被支配の関係も人一倍よく分かっていたのではないでしょうか。一つ興味深い話を紹介すると、第3篇で登場する空飛ぶ島ラピュータは、その下にあるバルニバービ島を支配しています。これはラピュータ=イングランド、バルニバービ=アイルランドと読みかえることもできますよね。実際、ラピュータというのはスペイン語のla putaすなわち娼婦を意味しているという説があって、これをスペインの「娼婦に気をつけろ、財布を空にされるぞ」ということわざと結びつけて、ラピュータがアイルランド経済を破壊する娼婦すなわちイングランドの寓意だとする解釈もあるようです。(『『ガリヴァー旅行記』徹底注釈[注釈篇]』、富山太佳夫ほか、岩波書店、p.273)
アイルランドが植民地として支配される実態をおそらくスウィフトはよく理解していた。だからこそガリヴァーに植民地批判をさせたのでしょう。しかしそこはさすがスウィフトで、直後にイギリスの事ではないよと言ってのける。そこにはイギリス人たらんとしながらも、そうもいかなかった彼のイギリスに対するひがみのようなものが感じられます。
◆あとがき
vol.17のエラスムスから今回まで、一応僕の中ではひとつらなりの話です。今回のガリヴァーではロビンソン・クルーソーやラス・カサスの『簡潔な報告』と話をつなげましたが、人々の愚を抉り出すという点ではエラスムスの『痴愚神礼賛』と通底するところがありますし、フウイヌムという一見理想郷らしきものが描かれている点では、トマス・モアの『ユートピア』とも重なります。実はガリヴァーという名前も、「愚者」といった意味があるらしく(Gulliverと綴りが近いgullibleという単語は「だまされやすい」「のろまな」といった意味)、このことは、ユートピア島について語ったヒュトロダエウスという架空の人物の名前が「馬鹿話の達人/売り手」といった意味のギリシア語の造語だったことともうまく対応しています。ラブレーについて言えば、ガリヴァー旅行記でもラブレー的スカトロジーは健在ですし、18世紀啓蒙主義の巨人ヴォルテールも彼の『哲学書簡』でスウィフトのことを「イギリスのラブレーといわれる創意にあふれたスウィフト博士」(林達夫訳、岩波文庫p.183)と書いています。vol.22の世界システム論にしても、アイルランドとイギリスの話に関して言えば、イギリス=「中核」、アイルランド=「周辺」と位置付けることもできるでしょう。
そんなわけで、ここ数カ月は過去の汗牛足の内容と絡めた込み入った話が多かったので、読者の皆さんにとっては読みにくかったのではないかと思います。その上ほとんどが古典だったので、とっつきにくい本が多かったかもしれません。興味のない人にとってはサッパリ、というところでしょうか。一方でぼくの汗牛足を読んで、取り上げた古典を読んだつもりになっている人がいないか心配です。ぼくとしてはこの汗牛足を一つのきっかけにしてぜひ実物に手を伸ばしてもらいたい、そして自分なりにその本と格闘し、自分の糧にしてもらいたい、それがぼくにとって一番うれしいことです。いずれも必ず発見があるような素晴らしい古典です、ホントに。皆さんが自分なりに古典を読まれることを願っています。そして、読んだらぜひぼくに議論を仕掛けてほしい。何年でも待ってますから!
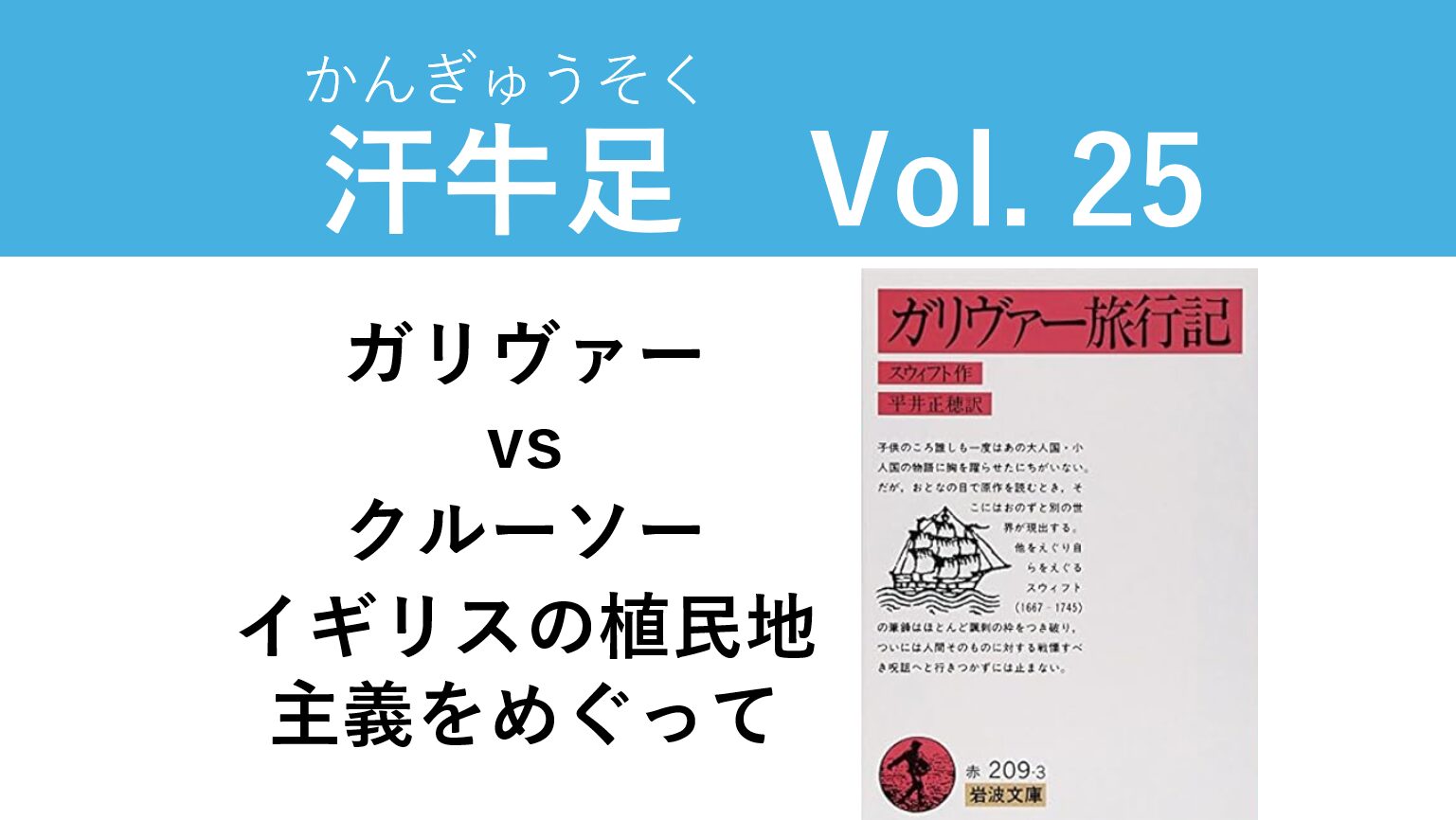


コメント