「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.28 (2018.4.14発行)
◆前回は脳科学の話から始まったのに最後は死刑の話まで飛んでしまいました。なぜ急に死刑の話になったかと言えば最近の関心事だったからで、つい思いつきで皆さんに死刑の存廃などについて質問までしてしまいました。回答してくださった方に改めて感謝します。
死刑の話になったのは、実を言うとある本を読んでから改めて死刑について考えさせられて以降、この問題が頭から抜けきらなかったからでした。今回はその本を取り上げて、いただいた回答もおいおい紹介しようかと思っています。
■萱野稔人(2017)『死刑 その哲学的考察』ちくま新書
死刑は命を奪う刑罰である以上、当然重いテーマになりますが、それについて本書とともに考えをめぐらせることはとても良い哲学的思考の練習になるとともに、筆者の論展開はなかなか鮮やかで、楽しませてもらいました。「哲学的考察」と聞くと難しそうで読む気がしないという人もいるかもしれませんが、文章は平明でくどいくらい丁寧なので理解はしやすいです。この本のよいところは、「死刑は廃止すべきだ」「廃止すべきでない」といった結論ありきの議論ではなく、あくまで死刑そのものについて考察しよう、結論はその上で導き出そう、というスタンスを取っていることです。一方で私は前回、死刑の是非について皆さんに意見を求める前に、自分が死刑には否定的な立場にあることを書いていたので、死刑もやむを得ないと考えていた人には答えにくかったかもしれず、公平さを欠いていたのではないかと反省しています。また、「死刑を正当化する論拠は2つしかありません」と書いていたのも、改めてよく考えると根拠に乏しく浅薄でした。
(なお、前回は脳科学の観点から犯罪者の責任は問えるものなのか、問えない性質のものなら犯罪者にはどのように対処すべきか、という問いを立てましたが、責任が問えないとなると死刑うんぬん以前に刑事司法制度を全面的に改めなければならないので、ひとまず今回は犯罪者の責任は問えるものと仮定しておきます。今回はあくまで死刑の是非がテーマですし、紹介する本の中でもその点については触れられていませんでした。)
さて、本書は結論を出す前に死刑をめぐって4つの観点で考察しています。1つ目は、死刑の是非は普遍的に結論付けられる問題なのか、それとも国や文化によって答えが違っていいという相対的な問題なのか、というもの。いきなり普遍主義と(文化)相対主義という哲学の一大テーマが出てきて私などはとてもワクワクする問いです。
文化相対主義の立場からは、死刑制度はその国の文化的な価値観に立脚したもので、死刑廃止が普遍的に正しいとは言えない、といった主張がなされます。日本政府はどうやらこの立場のようですね。2002年に当時の日本の法務大臣が国際会合で、日本が死刑を存置しているのは、「死んでお詫びをする」という言い回しがあるように、日本独特の罪悪をめぐる文化的な背景があるからだ、という趣旨のスピーチをしたそうです。この発言に対してはヨーロッパ側で批判があったらしく、(普遍主義の立場からすると)死刑は人権にかかわる問題であり、文化によって決められる問題ではなくて普遍的な問題として議論されるべきだ、とのこと。ポイントは、死刑は日本の文化と言えるかどうか、というところではなくて、たとえ日本の文化だったとしてもそれを根拠に死刑を正当化できるのか、ということ。あるいは、2014年の内閣府の世論調査によると「死刑もやむを得ない」と回答した人は80.3%でしたが、たとえ8割の日本人が死刑を存置すべきだと考えていたとしても、それによって死刑を正当化できるのか、ということです。
死刑は文化の問題で、その国や地域の多くの人間がそれでいいと思っているならやむを得ないのではないか、という意見があるのは当然でしょう。しかし著者が挙げるこんな事例を見るとどうでしょうか。イスラム圏では現在でも、不倫をすると姦通罪に問われて石打ちの刑(残虐な死刑)にされる国があります。大きすぎる石ではすぐに死んでしまうので「ほどよい」大きさの石を使うそうです。また、「名誉の殺人」というのは、婚前交渉や婚外交渉などを行った女性を家の名誉をけがしたとしてその父や男兄弟が殺してしまうというもので、おもに中東や南アジアで行われているのだとか。これはあくまで私刑ですが、多くの場合公権力に黙認されているそうです。たしかに現地の人々はそれを当然のこととして見ているのかもしれませんし、そういう「文化」なのかもしれませんが、だからといって女性蔑視や冤罪を助長しかねないこのような風習を正当化できるでしょうか。
このような事例に対しても文化相対主義の立場をとることは、その悲惨な現状を肯定することと同じです。そのような風習はなくすべきです。そしてその主張を根拠づけるには、やはり人権概念などの普遍的価値に立脚することが必要です。
話は変わりますが、死刑の是非についての前回の質問に対して、生まれた時から死刑がある世代はいいと考えていても、まだ生まれていない後の世代のことを考えれば早く廃止すべきだ、と回答してくれた方がいました。私が共感し、評価するのは、将来世代にとってどちらがより望ましいのか、というその観点です。不倫した(とされた)人に対する石打ち刑や、名誉の殺人といった悪習は、今廃止しなければ、そこで生まれてくる将来世代もその悪習を自明視するようになるでしょう。いま改めなければ、これから先の世代をも犠牲者になるのだ、といった未来への視座を持つことで、何が正しいか、何が必要なのか、といったことがよりハッキリと見えてくるのではないでしょうか。
さて、いまあなたは人権擁護の観点から普遍主義の立場に立って上記の「悪習」を批判するとします。それに対して相手は文化相対主義の立場に立ってそれは文化の問題だ、我々はそれを問題とも思っていない、などと反論してきたとしましょう。しかし普遍主義の立場からすると、その「悪習」はこの人権侵害という普遍的「悪」だからこそ批判しているですから、この反論は何も言っていないに等しいことなのです。相手が言わなければならないのは、自分たちの「悪習」を文化相対主義で擁護することではなく、自分たちの「悪習」が人権の侵害に当たらないことを論証するとか、自分たちの「悪習」あるいは「文化」が人権よりも優先される理由を説明しなければならないはずです。このとき、その論証ないし説明は普遍主義の立場に立つより他ありません。普遍主義と文化相対主義とが対立したときには、文化相対主義の側は必然的に、普遍主義の立場に立ち直して、相手に反論する必要があるといえるのではないでしょうか。
死刑は文化の問題だ、と主張したいなら、死刑は人権を侵害するものである(しかねないものである)という批判に対して、その批判が当たらないことを普遍主義の立場から反論しなければなりません。このとき、死刑の正当化には論理的な根拠が必要であって、決して文化や世論によって相対的に正しいものだとすることはできません。だからこそ死刑は普遍主義の立場から扱われるべき問題だ、というのが本書の第1章での結論です。
気付けば本書の4つの観点の一つ目の紹介で長くなりました。これはむしろ議論のための土台であってここからが本番なのですが、どうしてもざっくりとした説明になるので、詳しくはぜひ本書を手に取ってほしいと思います。
2つ目として、死刑が「悪用」された事例を見た上で、死刑の犯罪抑止力の問題に取り組みます。「自分の人生を幕引きする代わりに他人を道連れにしてやろうと考えた」(宅間守)、「死にたいが先です。そのための手段が死刑です」(金川真大)、「自殺しようと現場近くで刃物を買ったが死にきれず、人を殺したら死刑になると思った」(磯飛京三)といった身勝手な凶悪犯の例が紹介され、彼らに対して死刑は刑罰として意味を持っているのか、むしろこの場合死刑は犯罪者に「死への逃避」を許す無力さをあらわにしているのではないか、という問いが突きつけられます。一方で、だからといって現行の絞首刑よりも苦痛を与えるために火刑などの刑を日本が導入しようとすれば、憲法第36条の「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」に明らかに抵触しますし、国内外からの猛反対がなされることは目に見えていて、現実的ではありません。つまるところ、安楽に死なせないならば残虐刑にたどり着き、安楽に死なせるなら死への逃避を許して刑罰としての意味を失う、というジレンマを死刑は必然的に伴っているのではないでしょうか。
残虐刑への道は閉ざされている以上、この点からは死刑は支持されないでしょう。どうせ有罪なら死刑になってさっさと「終わらせ」たいという犯罪者を予防するには、「終わらせ」ない刑罰が最高刑である必要があります。となると、現行の無期懲役や、あるいは無期懲役から仮釈放をなくした終身刑を導入する、という選択肢が視野に入ってくるでしょう。前回の私の質問に対して、死刑を廃止にして終身刑を導入するのがよい、と回答してくれた方もいました。「簡単に死なせない」という点では終身刑はむしろ積極的な意味を持っているものと評価されてよいと思います。
3つ目の観点は道徳です。カントの定言命法なども出てきてこれも大変面白いのですが、書いているとキリがないので結論のあたりだけ紹介します。筆者によると「道徳的に正しい」と人々が判断するのは応報論が成り立っているときだけだ、とのこと。応報論というのは、「私が人にすること」と「人が私にすること」が釣り合わなくてはならない、ということで、「価値の天秤」に例えられます。殺人という犯罪が天秤の片方にあるならば、もう片方にそれに見合うものが必要で、それが釣り合ったなら道徳的に正しい、と考えるわけですね。釣り合うことが正しいことだ、ということが普遍的に認められているからこそ、道徳には説得力があると言えます。しかし何をもう片方の皿に持ってくれば天秤が釣り合うのか、については、普遍的に正しい答えはなく、むしろ相対的なものにならざるを得ない、というのが著者の見方です。この観点からすると、死刑賛成派は例えば殺人という犯罪に対して死刑こそがそれに道徳的に見合う刑罰だとするのに対して、死刑反対派は心からの反省や更生への努力、あるいは一生自由を失う終身刑こそが、殺人に対して道徳的に正しい刑罰だと主張している、というふうに見ることができます。
前回の汗牛足に対しては、死刑については長年にわたって議論されてきたのに事態が一向に変わらないことそのものが議論の対象になるべきではないか、との意見もありました。これについては、やはり賛成派と反対派との間で、凶悪な犯罪者に対してどのような処置が下されるのが(道徳的に)正しいことなのか、をめぐって水掛け論が続いてきたことが一因としてあるように思います。「凶悪な殺人犯は死をもって罪を償うべき」という主張と、「殺人犯にも更生の可能性はあり、その機会を奪ってはならない」とか、「死なせるのではなくて、死ぬまで一生罪を償わせるべきだ」といった主張がぶつかっても議論は平行したままで、どちらがより雄弁に語って人々を納得させられるか、という不毛な議論になりがちです。これでは対立が一層ひどくなりかねませんし、そもそも何を持ってくれば価値の天秤が釣り合うかということは文化的背景や時々の状況によっても、もちろん個々人によっても考えが異なって当然です。日本で殺人犯は死刑になるべきだと考えている人も、中国で麻薬の密輸をした罪で日本人が死刑にされるとそれは重すぎるのではないか、と思う人も多いはずです。道徳の天秤で何を持ってくれば釣り合うかについては、普遍的な回答はなく、相対的な問題だというべきでしょう。したがって、死刑を道徳的に肯定する究極的な根拠はありませんし、道徳的に否定する根拠もありません。死刑は道徳の問題では決着がつかない、というのを読んで私はとてもスッキリしました。
4番目に、政治哲学の立場から死刑を考えます。この観点からは、死刑の権限を保持している公権力と保持していない公権力のどちらが望ましいか、ということが問題になります。ここで問題になるのがやはり冤罪で、つまり自由を奪う自由刑ではなく生命を絶つ生命刑である死刑は、冤罪の場合取り返しがつかないということが問題になります。これに対して、冤罪は単なるミスであり、問題はそのミスをいかに極力減らすかであって、死刑の是非とは関係がない、とする主張があり、著者はこれに反論しています。誰とは言いませんが、「犯人」を捕まえないとメンツが傷つく人々や、容疑者を起訴するからには有罪にしなければならない人々、被告人に「騙される」ようなことはプライドが許さない人々が関わるので、冤罪はどうしても起きてしまうものでしょう。また、冤罪は公権力によるれっきとした人権侵害である以上、電車や自動車の事故とはまったく性質の異なるものです。著者は冤罪の危険性は原理的に排除できないことや、冤罪は公権力の正統性を危うくするものであることを挙げ、この観点から死刑は廃止すべきだとしています。
日本ではさすがに冤罪で死刑なんてないだろうと思っている人もいるかもしれませんが、それは甘いです。本書では飯塚事件という1992年に起きた事件の事例が取り上げられていますが、これなどは背筋の寒くなる話でした。冤罪については個人的に興味を持ったので、できればまた改めて取り上げたいと思います。
さて、以上で本書の結論は出ました。死刑は廃止すべきだということです。ただし、これはあくまで著者の「哲学的考察」から導かれたもの、ということもできるでしょう。あなたも自分なりに「哲学的考察」をして、著者の論をよく吟味してみることは大いに意味のあることだと思います。
◆おわりに
とはいえ、本書での結論は、死刑制度を肯定する根拠、否定する根拠についての一考察の結果であり、いわゆる理論であって、実践ではない、それでは意味がない、という意見の人もいるかもしれません。80.3%もの人が死刑もやむを得ないと考えているなら変えようがないとか、そんな理想論はあっても無力だ、そんな暇があったらもっと実践的なことをやるべきだ、という考え方もあるでしょう。というのは実際に前回の汗牛足の質問に対してそのような意見もあったからです。
私は自分では、いわゆる理想主義者でも現実主義者でもないと思っています。時には現状をつぶさに観察し、接触する、新聞・雑誌や新書などで今自分が生きている世界を知る、その一方で、時には現実から距離をおいて根本に帰る、あるいは哲学する、古典と対話する、歴史を訪ねる、ということが私にとっての「理想」です。そうやって<理想>と<現実>の間を行ったり来たりしながら、なるたけ<現実>が<理想>の方に少しでも近づくように努力すればよいのではないかと。だから理想論にも意味はあると思いますし、一方でその理想が意味を成すためには現状への関心と認識が求められるでしょう。あるいはその理想に大局的に近づくために、短期的には理想をカッコに入れて、現実的に、戦略的に考えなければならない時もあるだろうと思います。
最高刑として生命刑(死刑)があるのと、生命刑はなくて自由刑があるのとではどちらが好ましいでしょうか?私は後者だと断言します。理由はただ一つ、冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかないこと。そうした可能性を原理的に排除するには死刑を廃止するよりほかないからです。そうである以上、日本の死刑も廃止されるべきだと考えます。そしてここまでは世論と関係のないことです。
日本の死刑は廃止すべきだ、という結論が出たところで、この主張が他の人々にも納得してもらえるよう説得力を持つにはどうすればよいか、という問いかけから実践への道が開けてくるでしょう。本書でも最終章がそれにあてられています。筆者によれば人々が死刑を支持する最大の要因は処罰感情であり、処罰感情が冤罪への問題意識と相反するものであるために、冤罪の問題が軽視されているそうです。しかし、だからといって処罰感情を否定することはできません。したがって死刑廃止をとなえる以上、その処罰感情にどのように応えるのか、ということが課題になります。そしてその意味で死刑の代替刑として終身刑を導入することがカギになるのです。先にも書いたように、「死への逃避」を許さないという点で、終身刑は死刑よりも厳しい刑罰になりえるものです。世論調査では、死刑賛成派の中で終身刑を導入するなら死刑を廃止してもよいと回答した人は4割弱でした。こういった人々を増やしていくことがやはり死刑廃止への条件となるのではないでしょうか。
そして何より、この汗牛足を読んで、あなたの死刑に対する考えが深まったなら、それがとりもなおさず最も初歩的な意味で「社会が変わる」ということだと思います。社会を変える第一歩は、自分を変えるということ以外にあり得ません。自分を変える以上、より綿密な現状認識と問題解決のための考察・思索はあって当然です。その考察の産物が「理論」ないし「理想」だと言われようと、それこそが最も基本的な意味での「実践」だと私は思っています。そしてこの汗牛足がそのきっかけになれば、それが私にとって最も嬉しいことです。
(参考資料)
内閣府世論調査
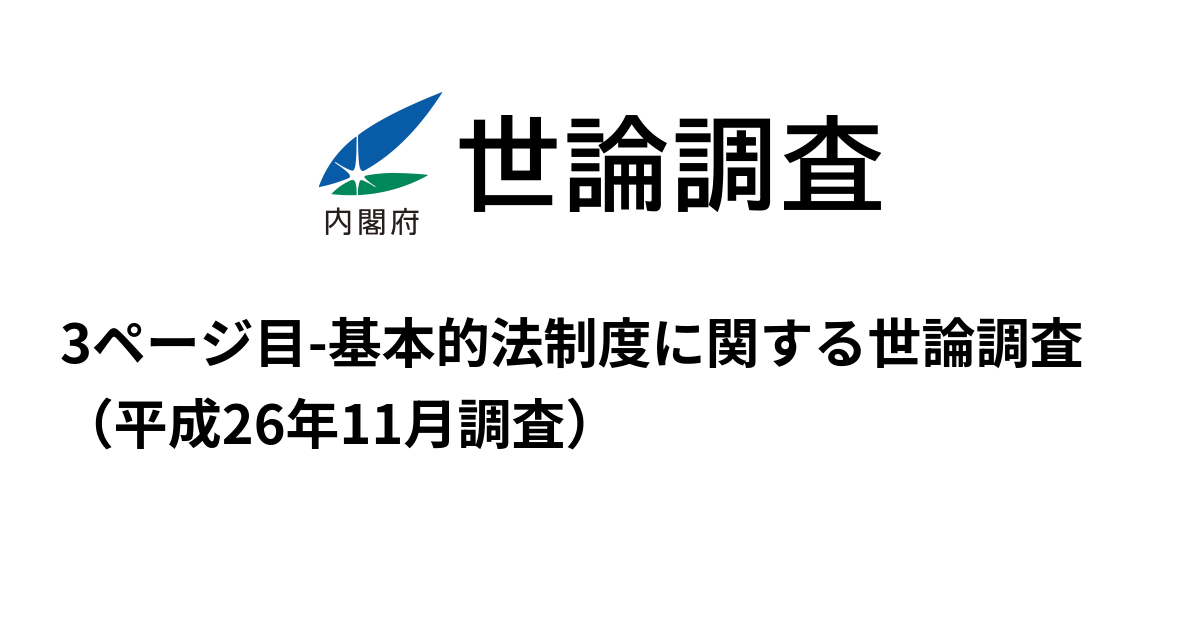
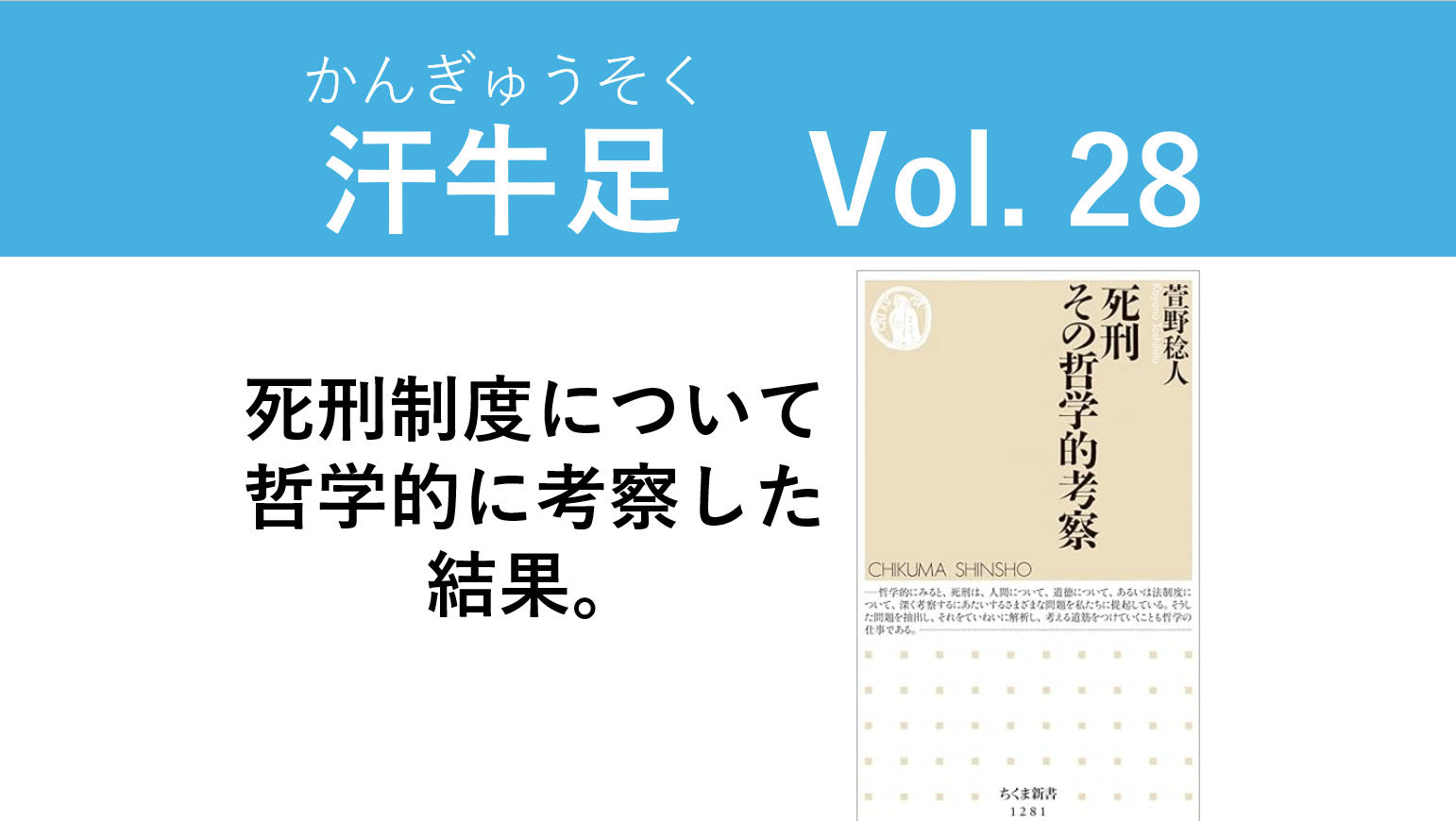


コメント