この記事は2023年10月にサービスが終了した読書サイト『シミルボン』に投稿していた記事である。ボクの日記から推定すると、記事の公開は2020年11月頃。
デュルケムの『社会学的方法の規準』(1895年)を読む試みです(第3回/全3回)。前回はこちら。
第四章 社会類型の構成にかんする諸規準
前章で述べられたように、ある社会的事実が正常か、病理的であるかは社会の種類、「社会種」によって異なる。では、社会種はどのように構成し、分類すればよいかというのが本章での課題となる。デュルケムによると、分類を行うことの意義は、次のようになる:
分類が真に有用になるのは、分類が、その基礎となった諸属性以外の属性を分類することを可能ならしめるとき、いいかえればあらたに生じる諸事実にたいする枠組みを与えてくれる場合にかぎられよう。(p.172)
そこで、分類にとって本質的な少数の属性を見出すことが必要となる。デュルケムによれば、「一つの民族は、それに先行する二つあるいはそれ以上の民族の結合から生じている」ため、もっとも単純なレベルの社会の構成要素が、まさにその属性として採用される。次に、その構成要素がどのように結合してより複雑な社会を形成していくかによって、社会種が分類できるというヴィジョンを提示している。しかし、本書では具体的な分析や提言等はほとんど行われていない。
第五章 社会的事実の説明にかんする諸規準
本章では、社会的事実をいかに説明すべきかということが問題とされる。デュルケムによれば、先行する社会学者による社会現象の説明は目的論的であり、同時に心理的でもあるという。彼らは社会というものは人々が目的意識を持って形成したものであるという立場を取るので、社会を規定するものは個人の意識ないし心理ということになるからだ。
一方のデュルケムは第一章で社会的事実を「個人にたいしては外在し、かつ個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力」として定義していた。これは個人に対する社会的事実の外在性を主張するものである以上、デュルケムとしては「社会現象は個人の意識から派生するものではない」のである。では、社会は何によって形成されるのか?ここでカギとなるのは、「結合」という原理である。この原理に関する記述は、今日「創発」と呼ばれる現象をデュルケムなりに表現した個所として興味深いので、少し長くなるが引用する:
だが、こういう異論があるかもしれない。社会を形成している要素といえば個人しかない以上、社会学的現象の最初の起源は心理学的なものでしかありえないのではないか、と。だが、もしこうした推論に拠るならば、おなじく容易に、生物学的諸現象は分析的には無機的現象によって説明されるという主張をなすこともできる。じっさい、いかにも生物細胞のうちには無機質の分子しか存在しない。しかしながら、そこでは諸分子は結合しており、この結合こそが、生命を特徴づけるそれら新しい現象の原因となる。そして、この現象については、その萌芽ですら、結合している諸要素のいずれのうちにもみいだすことができない。それというのも、全体はその諸〻の部分の総和(somme)とは異なるある別ものであり、その属性は、それを構成している諸部分の示す属性とは異なっているからである。結合(association)とは、一般にしばしば考えられてきたように、獲得された諸事実と構成された諸属性を単に外部的に関係づけるにすぎない、それ自体では不毛な一現象なのではない。それどころか、それは、諸物の一般的な進化の過程であいついで生じてきたいっさいの新しい事実の源泉なのではなかろうか。(pp.206-207)
システム(社会)は独立した要素(個人)から構成されているはずなのに、それ自体として独自の振る舞いをする。だから「集団は、その成員が個々に孤立して行うのとはまったくちがった仕方で、思考し、感覚し、行動する」のである。ここから、社会的事実を説明する上での規準が提示される:
社会的事実の決定原因は、個人意識の諸状態ではなく、それに先立って存在していた社会的諸事実のうちに探究されなければならない
第六章 証明の実施にかんする諸規準
前章で社会学的事実の原因を説明する方法上の規準が示されたが、本章ではその因果関係を証明する際に従うべき規準が示される。社会的な諸現象は人為的な対照実験ができないが、そのような条件のもとでどのようにして「証明」が可能なのだろうか。
ひとつの現象が他のひとつの現象の原因であることを証明する手段は、われわれにとってひとつしかない。それは、この二つの現象が同時に出現しているか、もしくは同時に欠如しているようないくつかの事例を比較し、状況のさまざまな組み合わせのなかで両者の示す変動が、果たして両者の依存関係をあらわしているのかどうかを調べてみることである(p.239)
しかし、社会学では条件を変えて実験することができないので、社会現象に関する一連の事例を複数集めてきて、それらを比較する、という「比較的方法」を採らざるをえない。比較的方法の中でも、社会学において有用なのは「共変法」だとデュルケムは書いている:
じっさい、この方法[共変法]が論証的であるためには、比較のなされる諸変化以外のいっさいの変化が厳密に排除される必要はないのだ。二つの現象が変化しつつ示す値のあいだのある並行関係が、充分な変化のみられる事例において充分な数量において確認されさえすれば、それだけで両者のあいだにひとつの関係が存在することの証拠となる。(pp.246-247)
しかし、よく言われるように、二つの現象が関係があるということと、因果関係があるというのは同一ではない。
併存という事態が、現象の一方が他方の原因であることによるのではなく、両現象がともに同一の原因の結果をなしていたり、さらには、その二つの現象の間に一方の結果であるとともに他方の原因でもあるところの第三の現象がひそかに挿入されていたりすることによる場合も、ありえないことではない。したがって、この方法[共変法]からみちびかれる諸結果は、さらに解釈をくわえられることを必要とするのだ。(p.248)
そのような例として、デュルケムは「自殺への傾向」と「教育を求める傾向」を挙げる。彼によれば、両者は足並みをそろえるように変動するため、両者のあいだには関係があるが、一方が他方の原因なのではない。両現象には共通の原因、すなわち「知識への要求と自殺への傾向を同時に強化する、宗教的伝統主義の衰退」があるとする。
当然、ここでは何をもってある現象を他の現象の原因と判断するのかが問題となるだろう。デュルケムはその点について一応書いてはいるのだが、漠然としていて、筆者の読む限り要領を得なかった。
社会現象AとBの連関について説得的な議論ないし解釈というものは可能であるとは思うが、それは「AはBの原因である」という「因果関係の証明」とは別ではないか。そもそも因果関係とは何か、それは「証明」可能なものか、というテーマについては、また改めて考えたい問題である。
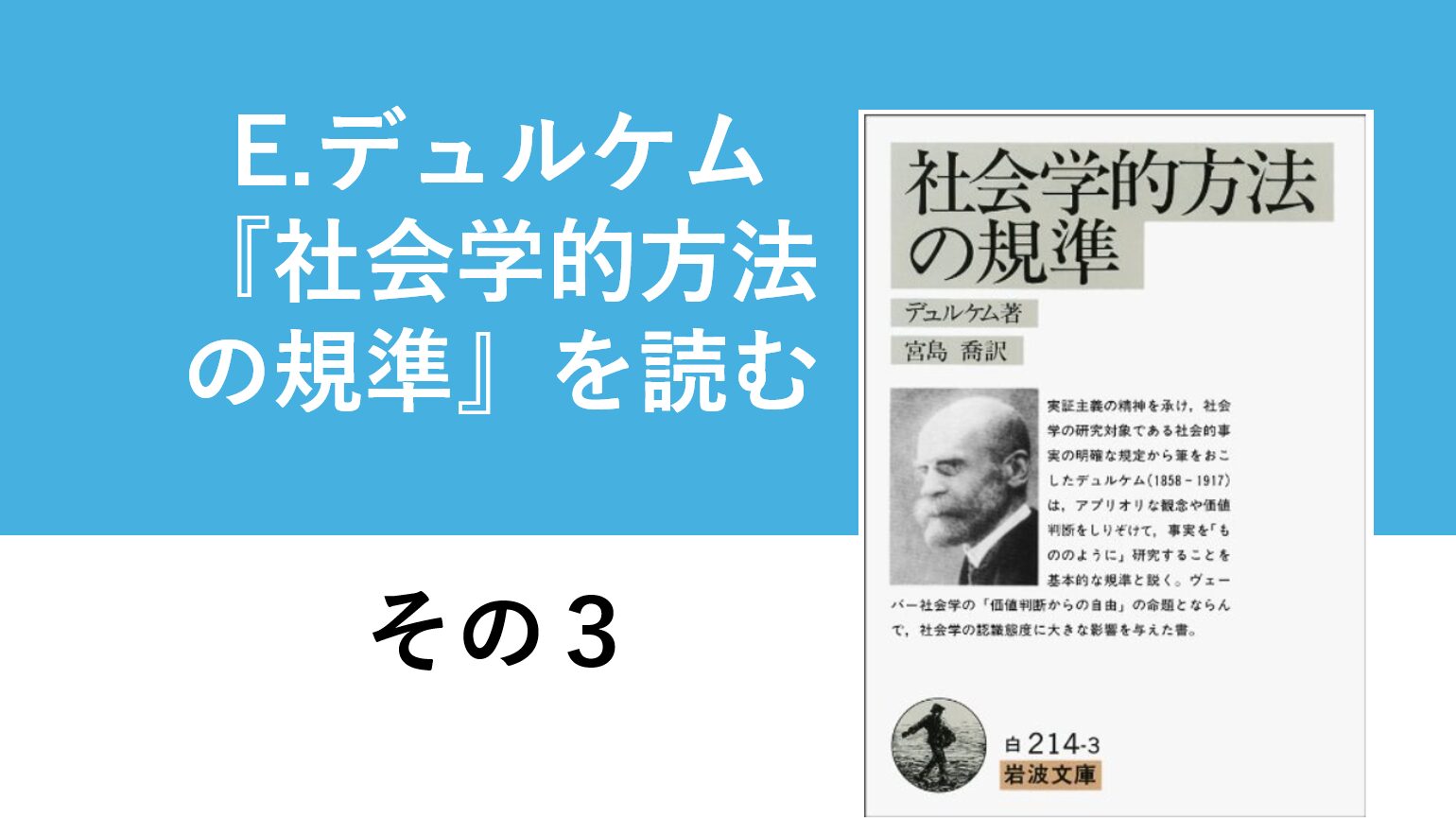


コメント