この記事は2023年10月にサービスが終了した読書サイト『シミルボン』に投稿していた記事である。ボクの日記によると、記事の公開は2020年12月20日。
1927年の創刊以来、現在まで存続する岩波文庫に収められた数々の作品の中でもおそらく最長のタイトルを有する本は、早くも創刊翌年の1928年に出版された。そのタイトルは、『イワーン・イワーノウィッチとイワーン・ニキーフォロウィッチとが喧嘩をした話』である。
19世紀ロシアの作家・ニコライ・ゴーゴリ作の小説で、2018年にリクエスト復刊された際に購入したまま放置していたのだが、先日何とはなしに一気読みしてしまった。一気読みをしてしまうほど、ついつい読み進めてしまうくらいの魅力はあったのだが、結局大したオチもなく、釈然としない。
舞台は19世紀初頭のロシアの片田舎で、とても仲の良かった2人の小地主が、ある日なんでもない出来事をきっかけに大喧嘩し、裁判沙汰になる。法廷に豚が闖入して訴状をくわえて持ち去ってしまうというゴーゴリ的ナンセンスなど読みどころもあるが、なんとも言えない結末となって幕を閉じる。
ゴーゴリの筆は登場人物の言動や容姿については饒舌なまでに描出してその点は満腹なのだが、心理描写はないに等しく、親友だったはずの2人がどのような内面的葛藤を経て互いにかくまで反目するに至ったのか、合理的に理解するのは困難だ。いや、そもそも人間の感情というのはかくまで不合理だというメッセージなのか、あるいは悠々自適の生活を送る小地主特有の、私には理解不能な内在的論理が働いているのか。
彼らが喧嘩をしている理由は結局よく分からないものの、一つ確かなことは、彼らには徹底して喧嘩をする余裕があったということだ。資本主義社会の一パーツとして忙しい毎日を送る現代人には、他人の庭の様子をのんびり眺める暇などないし、喧嘩のために雄弁な訴状を執筆する余裕もない。都市社会の人間関係は一般にドライであって、十年以上いがみ合うほど濃密な関係を維持するのは困難だ。
有閑階級の特権としての喧嘩を描写した本書は、その特権を有しない私に自らの環境を否応なく相対化させる。喧嘩と聞くとネガティブなイメージを持たれるかもしれないが、実は人間のエネルギーの詰まった文化的行為なのだ。「火事と喧嘩は江戸の華」という文句があるが、東京ではどちらもしぼんでしまった。火事がなくなるのはよいが、喧嘩がないのは文化的貧困の兆候かもしれない。だから私もいつの日かこう叫んでみたい、「諸君、此の世は退屈だ!」と。
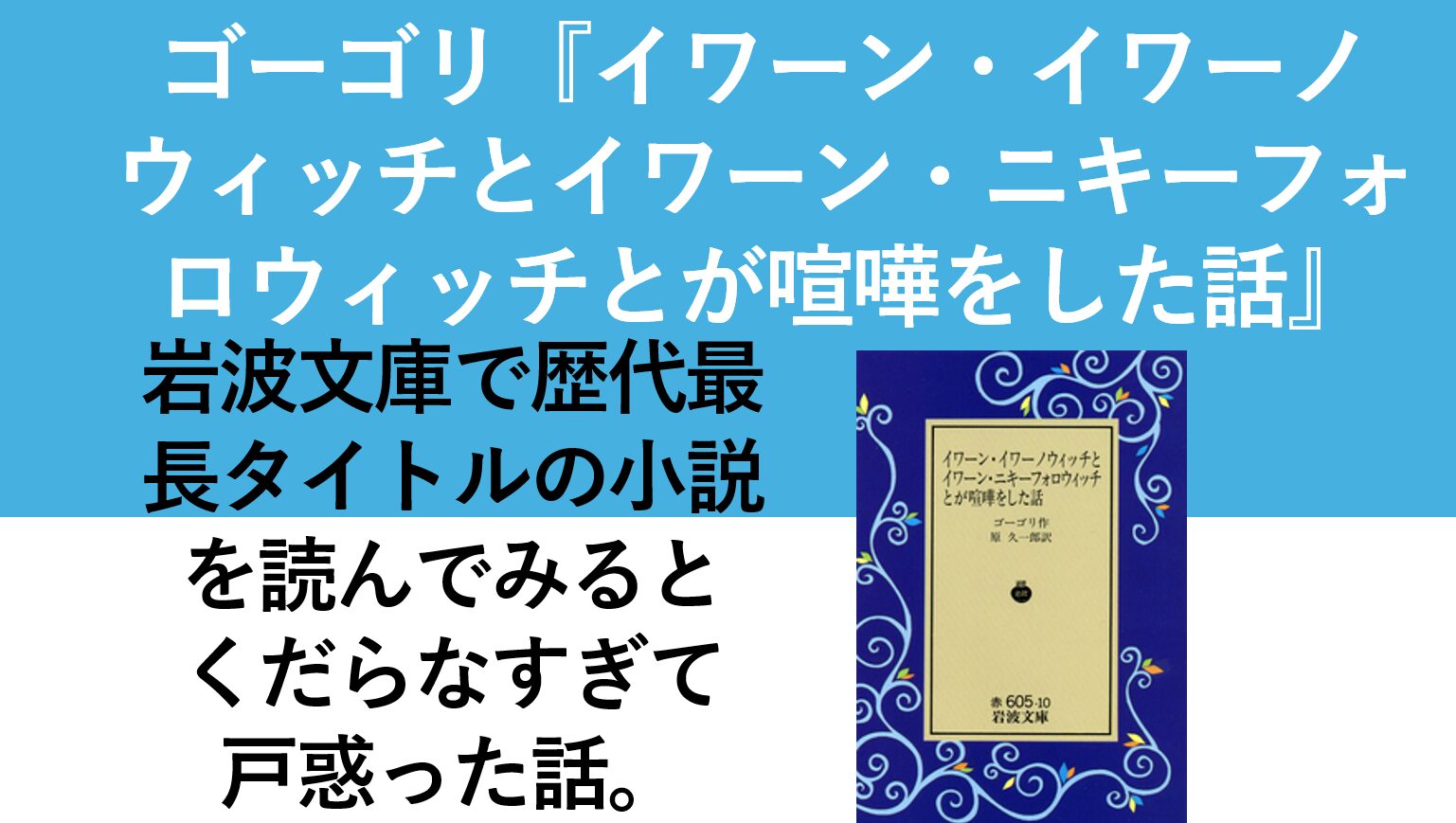


コメント