「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.29 (2018.5.12発行)
◆前回は重いテーマですが死刑について書かせていただきました。ですから今回は明るいテーマを取り上げ……たいところですが、今回も比較的重いテーマなんです。ごめんなさい。
今回のテーマはズバリ、冤罪。罪を犯していないにもかかわらず罰せられるなんて、そんなことめったにないだろうし自分には関係ないよ、と思っていませんか。まあ私もこれまではなんとなくそう思ってきたのですが、いろいろ調べてみると、そんなに呑気なことを言っていられるほど、日本の現状を楽観視できないと思うようになりました。
○はじめに
数カ月前に、『99.9』というドラマ番組が放送されていて、弟が熱心に見ていたので私も少し見ました。このドラマは刑事事件専門の弁護士が裁判をひっくり返して無罪判決を勝ち取るというスジなのですが、ウン、たしかにおもしろい。でもどうしてそんなタイトルなのか。調べてみると、これは日本の刑事裁判における有罪率の数字を意味していたようですね。しかし99.9%というのはさすがに誇張だろうと思っていたのですが、今回紹介する『冤罪と裁判』(2012)によると、決して誇張ではなくて、半世紀以上前から相当高いようです:
1950,51年頃:98.3%
1955~75年:99.4~99.6%
1980~91年:99.8~99.9%
1998~2000年:99.93~99.95%
2005年:99.92%
2009.5.21~2012年1月末の裁判員裁判:99.64%
なお、その後の数字を私が調べると、だいたい年間5万強の有罪判決に対して100前後の無罪判決が出ているようです:
2012年度:99.9%
2013年度:99.8%
2014年度:99.8%
2015年度:99.9%
2016年度:99.8%
(司法統計年報(www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search)より、各年度の刑事事件編「9 刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員 地方裁判所」の表から、(有罪率)=(有罪)/(有罪+無罪)×100[%]で小数第2桁を四捨五入して算出。)
刑事事件で無罪になるのはかなり珍しいことはわかります。問題は、この有罪率の数字が良いか悪いかという以前に、なぜほぼ100%有罪なのか、ということですよね。私が思うに、ざっくり2つの要因があると思います。
①実は無罪なのに有罪判決を受けている場合があること。
②刑事事件の被疑者(容疑者)を起訴するか否かは検察が判断しますが、その検察が「有罪が確実に見込まれる」場合だけ起訴して裁判にかけていること。
今回取り上げたいのが①の要因、つまり冤罪です。99.9%というのは②が原因だから問題ないとする意見もあるようですが、①の要因があることを無視することはできません。また、私は②についても、本来被告人の有罪・無罪は裁判官が判断すべきことなのに実質的に検察がそれを判断してしまっているという点で問題だと思っています。しかし今回は冤罪に話を絞って①について詳しく書くことにします。
■今村核(2012)『冤罪と裁判』講談社現代新書
内容は、どのようにして冤罪が起きるのかについて書かれた第1部と、裁判員制度によって冤罪を減らせるかについて書かれた第2部から構成されています。今回は冤罪そのものに論点を絞りたいので、主に第1部のみ扱うことにします。冤罪はどのように生まれるのか、冤罪事件の典型例の紹介とともに具体的に理解できて参考になる本です。ただし、2012年の本なのでそれ以後の制度改革は反映されていません。
第1部では、冤罪の原因となる証拠として虚偽の自白、目撃者の間違った証言、偽証、物証・科学判定の軽視、情況証拠の不適切な適用が挙げられています。それぞれについてザックリまとめるとこんな感じ。
虚偽自白:無実にもかかわらず罪を認め、どのように犯行に及んだか「自白」すること。逮捕されると起訴されるまで最長23日間拘束されて(自白すれば早く釈放されるというエサがある)、連日10時間ほどの取り調べを受ける。接見禁止処分を受けて家族にも面会できない場合がある。このような取り調べ(という名の精神的拷問)によって、無実の人は多くの場合自白に至る。しかし、「私がやりました」と認めるだけでは足らず、「どうやったのか」と問われて、捜査官のみぞ知る「正解」に達するまで取り調べは延々と続く。自白するといわゆる「自白調書」が作成され、これに署名してしまうと公判で否認しても裁判官はほとんど聞き入れてくれない。「裁判官ならわかってくれるはずだ」という期待は裏切られる。なお、逮捕されていなくても「任意」同行を求められて、署までついていくと、過酷な取り調べを受けて自白させられ、逮捕・起訴される、というパターンも相当あるので注意。
目撃者の証言:記憶違いでも、目撃者本人はそれに気づかず、法廷で無実の被告人を指さし、「この人が犯人です。間違いありません。」などと確信を持って証言する場合がある。その印象は強烈で信用されやすい。事件から数か月後、時には1、2年後に警察官が目撃者に写真帳を示し、そのなかに犯人がいるか、それはどの写真かと尋ねる。その写真選別の過程は録音・録画されていないので、警察官から示唆があったかどうか、目撃者に躊躇があったかどうかはわからない。目撃者はその後、選んだ写真の人物=容疑者を透視鏡越しに見せられ、誤りの記憶が強化される。
偽証:法廷で虚偽の陳述をすること。身近な人に対するウソの引っ込みがつかなくなって、結局法廷でもウソの証言をするケースや、警察官が検挙ノルマ達成のために偽証する場合などがある。驚いたことに、警察官の偽証に合わせて捜査機関が組織ぐるみで証拠を捏造した事例まである。留置場の同房者が警察とグルになって、「犯行告白」を引き出すという悪質な例もある。弁護側の証人は偽証罪に問われることがあるが、著者によると、「偽証により人を冤罪に陥れた者を日本の検察官が起訴した例を、私は聞いたことがない」という。
物証と科学鑑定:日本の冤罪・誤判の多くは自白や証言などの供述証拠に頼りすぎて物証=非供述証拠を軽んじていたことが原因としてある。逆に、再審による無罪は、新たに出てきた非供述証拠によって、矛盾する供述証拠を否定することで勝ち取られた場合が多い。一方で、捜査官が物証に作為を加える場合、証拠を捏造する場合がある。DNA鑑定でも、物象を採取、保管する警察官や、鑑定人の良心にゆだねられている面がある。日本では公的な法科学の研究・鑑定機関は、捜査側が独占していて、中立的・第三者的で公的な研究・鑑定機関がない。つまり、貧しく支援者もない被告人は弁護の視点から科学鑑定を受ける機会がない。
情況証拠:間接事実を証明するもので、間接証拠とも。例えば、「被告人を、犯行時刻ころ、犯行現場近くで見た」といった証言。あるいは、被告人の着衣に付着していた血痕のDNA型が被害者のそれと一致していた、とする鑑定結果もその一つ。間接証拠に関しては、(1)その間接証拠が間接事実を確実に証明すること(2)その間接事実から事件に関してどの程度まで言及できるのか見極めること、の2点を踏まえなければならない。ところが、この2点において証拠を過大評価したり、論理が飛躍したりする場合がある。(裁判官は法律の専門家であっても、日常経験は決して豊富ではないし、論理的思考に長けているとは限らない。)
冤罪の原因となる証拠はこのように様々なタイプがありますが、追加で書いておきたいのは、日本の刑事裁判は自白偏重である、ということと、検察官は集めた証拠をすべて開示することはしない(≒検察にとって有利な証拠しか開示しない)ということです。自白の任意性を担保するには、取り調べが苦痛とならないよう注意が必要ですし、その全過程を録音・録画する必要があります。ところが日本では「取り調べ」はほとんど拷問に近いことをやっていますし、それで得た「自白」を証拠として重視しているのです。(これでは魔女裁判と本質的に変わらないのでは?)
一方、証拠を収集する上で捜査機関側の方が弁護側よりも圧倒的に優位であるにもかかわらず、捜査機関は被告人に有利な証拠を持っていても公開しなくてよいのです!弁護人・被告人は検察が自分に有利な証拠を持っているかどうかも分かりません。日本の刑事裁判が公平というのは真っ赤なウソで、検察側の圧倒的優位のもとに進められているのが実態です。
冤罪の原因となるのは(ゆがんだ)証拠だけではなく、やはり裁判官の誤判という面もあるので、これについて以下で述べることにしましょう。
ご存知の方も多いと思いますが、刑事裁判においては、「疑わしきは罰せず」、あるいは「疑わしきは被告人の利益に」、という原則があります。これは多少単純化して言うと、被告人が有罪であることは検察が証明しなければならず、もしその立証に合理的な疑いの余地があれば裁判官は無罪判決を下すべきだ、ということです。言い換えると、被告人・弁護人は無罪の証明をする必要はなくて、被告人が罪を犯したとする検察の証明の誤り・不備不足を明らかにしさえすればよい、ということですね。刑事事件における冤罪は、事実として国家の個人に対する人権侵害であり、刑罰の目的にも反する以上、この原則は遵守されて当然のことだと思います。
ところが現実はどうでしょうか。日本の刑事裁判は一般的にこの原則に忠実であるとは到底言えない状態が続いています。一つの要因として、やはり裁判官が「有罪への流れ作業」に慣れきってしまっていることがあるのではないでしょうか。刑事事件の有罪率がキッチリ99.9%なら、ある刑事部の裁判官が年間200件もの判決を下したとしても、単純計算で5年間に1件しか無罪判決を出さない、ということになります。もちろん裁判官によって無罪判決を出す頻度は異なって当然ですが、平均して考えれば、裁判官にとって自分が無罪判決を下すのはオリンピックよりも珍しいイベントなんですね!(残念なお知らせを書けば、裁判官は事件処理数が多い方が人事上の待遇が良いそうですが、無罪判決に至る裁判は一般により多くの時間がかかるので、事件処理数の向上の妨げになるそうです。人権感覚の鋭い人、「疑わしきは罰せず」の原則に忠実な人は(刑事)裁判官に向いていない、少なくとも出世できないというのは何という皮肉でしょう!)
重要なのは、日本の刑事裁判ではほとんどの場合、裁判官は被告人が有罪か無罪かを判断するというよりも、被告人が有罪であることを確認して、その量刑判断を下すだけになっているということです。これが刑事裁判の有罪率99.9%が意味することです。こんなことでは、被告人の弁解や弁護人の弁護に向き合うことはおろそかになり、検察の起訴内容を認定するのに慣れっこになる裁判官が量産されても何の不思議もありません。有罪の証明がなされるまでは被告人は無罪であるとの前提で裁判が進められる、という「無罪推定の原則」というものがあるのですが、現実には「有罪推定」が原則になってしまっているんですね。ですから、この有罪率の数字は良くも悪くもない中性的な性質のものでは決してなくて、この国の刑事司法の機能不全の1つの象徴というべきものでしょう。
大多数の有罪判決のうち、いったいどれほどが「本当は無実」なのか。もちろんそんな数字は誰にも分りませんが、決して少なくはないだろうことは想像がつきます。「懲役刑を宣告されても、執行猶予が付いたり、刑期が短かったりすると、多くの被告人は、冤罪を叫びながらも司法に絶望してたたかうのをあきらめる」と著者が書いているように、あきらめの境地に達する人も少なくないのではないでしょうか。
最後に、今回紹介した本以上に見てもらいたい映画を紹介。
◇周防正行(監督)『それでもボクはやってない』(2007)
これは痴漢冤罪を扱った映画で、実際の事件をもとにしています。私は冤罪について多少の本を読んだ後にこの映画を見て、「百聞は一見に如かず」とはまさにこのことだと思いました。活字では伝わらない臨場感が伝わってくるのはやはり映像の強みですね。監督はおそらく、日本の刑事司法の冤罪を生みやすい体質、その理不尽さと、冤罪は決して遠い世界の出来事ではなくて、案外あなたの身近にありうる、ということを伝えたかったのだと思います。日本の刑事司法のおかしな点がよくまとめられているので、よかったらぜひ。
なお、33年間裁判官を務めたという瀬木比呂志氏は、『絶望の裁判所』(講談社現代新書、2014)という本の中でこの映画に言及し、次のように述べています:「実をいえば、私には、あの映画は、特にショッキングなものでも興味深いものでもなかった。なぜなら、ああいう事態がいつでも起こりうるのが日本の刑事司法の実態であることは、まともな法律家ならだれでもわかっていることだからである」。
刑事事件の裁判というのはそれなりにまともになされているんだろう、と私はなんとなく思っていたのですが、とんでもない。もはや日本の刑事司法なんて信頼できませんし、むしろ自分を冤罪に陥れかねない脅威ですらある、と思うようになりました。
○おわりに
私は刑事司法その他の法学分野にはまったくの素人なので、もしかすると誤っているところや説明不足なところ、ミスリーディングな箇所が多々あるかもしれません。いや、きっとあるでしょうからご指摘いただけるとありがたいです。
また、紹介した本は6年も前の本で、今回の汗牛足はその後の動向を正確に反映しているのでもありません。例えば、2016年5月に成立した刑事司法改革関連法はとりわけ重要な変化でしょう。これはもともと冤罪防止が目的の議論からスタートしたそうなのですが、事態は改善したかというと……うーん、ごくごく、ごく一部マシになったけれど、依然として問題は多く残ります。しかも、もともと冤罪防止が本題だったはずが、捜査力強化という論点が持ち込まれて、捜査機関側においしいアメが与えられてしまった、という感じです。特に、新たに導入された「司法取引」は冤罪につながりかねないもので、その点で事態は後退したように思います。司法取引は今年6月から始まるそうなので、今後どうなるか注目ですね。
***
さて、以下では、私が考えたことを蛇足ながら書かせてもらいました。(正直に白状すれば、書きたいことがまとまらず悪戦苦闘してやり場に困る断片が残されたのですが、捨てるのも惜しいのでここに追加した次第です。)
長くなるのでまた改めて読んでもらって結構です。
***
本書で紹介されていた冤罪事件の実例については全く取り上げられなくて残念です。いずれも悪寒が走るものばかりでした。私がそれらを読んでいて思ったのは、「こいつは○○に違いない!」と思ってその人を見ることがいかに危険か、ということです。被告人=犯人という思い込みがあると、その思い込みを強める事実にはよく気がつき、そしてしばしばそれを過大評価するのですが、その思い込みを否定する事実にはあまり目が向かず、過小評価する傾向にあります。
ところでずいぶん前に、この汗牛足でこんな問題を紹介したことがありました。(汗牛足vol.4、市川伸一(1997)『考えることの科学』中公新書)
問題.(四枚カード問題)
「A」「K」「4」「7」の4枚のカードについて、どのカードも片面にアルファベット、もう片面に数字が書いてある。そこで、「母音の裏側には、必ず偶数がある」というルールが成り立っていることを確かめるには、最低限どのカードをめくる必要があるか。
「A」をめくるべきだ、と誰もがとっさに思うでしょう。「A」をめくってみて偶数が出れば、ホレ、このとおりルールが成り立っておるではないかと。ところがしばしば「このルールが成り立っている」ということを示そうとはやるあまり、「もしやこのルールが成り立っていない例はあるだろうか」ということにはなかなか考えが及びません。つまり、当てはまらない事例はないのか、このルールの反証は本当にないか、ということはなおざりにしがちなのです。だから、奇数のカードをめくって母音が出たらルールが成り立たないことになってしまう!と気づける人はそんなに多くはない。こういうわけで、母音と奇数のカードをめくるべきだ、と言える人は、このルールを確かめようとしている人の中からはなかなか出てこないわけです。
冤罪事件の事例を見ていて、日本の捜査機関そして裁判所は、この例で言えば「A」のカードだけをめくろうとしているように思いました。そしてここではもちろん、「被疑者・被告人は犯人」というのが「ルール」になってしまっているのです。だから母音のカードしかめくろうとしない。奇数のカードなんてどうでもいいと思ってしまう。そんなわけで、おそらく知られている以上に冤罪は起きているし、被疑者・被告人の人権はないがしろにされているのです。多分この「被疑者・被告人は犯人」という「ルール」のもとでは、奇数もめくるべきだ、とどんなに言い聞かせても徒労に終わることでしょう。
一方で私たちもテレビや新聞で「先日の事件の容疑者が捕まった」と聞くと、まだ犯人と決まったわけではなくても、「犯人が捕まってよかった」とか、「こんな奴は死刑だ!」と思ってはいないでしょうか。メディアは捜査機関に(こびへつらって)提供してもらっている情報を垂れ流しているだけですから、我々はどうしても警察や検察側の見方(被疑者・被告人=犯人)をしてしまいがちです。(その上、凶悪事件ともなると一部メディアでは容疑者への人格攻撃で大盛り上がりです。)有罪判決が下されても、メディアはそれが妥当だったかどうか検証などしません。彼らの得意技は、「警察官・検察官=正義」と、「被告人=悪」というわかりやすい図式をつくることと、「公正」かつ「高潔」な裁判官によって有罪判決が下され、それが被害者ないしその遺族の無念を晴らすことに貢献した、というストーリーを喧伝することですから。
冤罪を防ぐためには何よりもまず、「疑わしきは罰せず」の大原則を、「無罪推定」の原則を、市民レベルから貫徹する必要がある、これは強く思います。そしてついでと言ってはなんですが、「警察・検察=正義」、「裁判官=無謬公正」という神話から人々が脱出できないとね……。
***
自分が支持するルールないし仮説・立場がまずあって、それを立証する事柄にしか興味がない、異論・反証には耳を貸さない、というこの問題はなかなか根が深いと思っています。例えば憲法論議。「改憲派と護憲派が喧々諤々の議論を……」というのは聞き飽きましたね。改憲派というのは、憲法は何が何でも変えなければならないもの、という「ルール」を守る人たちで、護憲派はその逆の人たち、とするならば、お互いが矛盾する「ルール」を信奉している以上、決着がつかないのは明白です。
あくまで守るべき立場ありき、結論ありき、で論争しても議論になりません。この問題について考えるには、まずそういった立場や「ルール」(煩悩と呼んでもよい)を極限まで捨て去り、対象そのものをなるたけ虚心に見るということが必要です。そして私が思うに、ここでいくつか毛色の違う議論が出てきます。憲法に関して言えばこのようになるでしょう。
(a)議題そのもの、議論の枠組みは守ったうえで、
(1)理念的な議論:憲法とは何か、どうあるべきか。立憲主義とは何か。憲法そのものの理想や理念に立ち返って憲法のあり方を問おうとする議論。
(2)実際的な議論:日本国憲法が実際にどのように機能しているのか。憲法に新しく必要とされる機能があるか。憲法を取り巻く日本社会の現状との関わりから憲法のあり方を問おうとするもの。
(b)議題そのものからは少し離れて、あるいは議論の枠組みそのものを批判し、
(3)哲学的な議論:そもそも憲法は必要なのか。立憲主義は法治国家における唯一の回答なのか。立憲主義よりも高次の概念、たとえば法治主義や、国の統治形態に立ち返って、そこから憲法のあり方を考えるもの。
(とりあえず3つ挙げてみましたが、他にもあるかもしれませんし、互いに重なる部分もあると思います。)
憲法の内容をよく吟味して、上記の(a)の議論を踏まえるなら、自ずから憲法のあるべき方向というものが見えてくるのではないでしょうか。こうした議論を踏まえた上で、「憲法のここは改めるべき」とか、「ここは変えてはいけない」という主張が、根拠・理由づけをともなって出てくるなら、憲法についての建設的な議論ができるでしょう。そして大切なのは、自分と異なる主張、自分より優れた主張がありうることを認め、相手の主張を否定したいならその根拠に対して反駁する、そして自分の主張の根拠に不備があれば、潔くそれを認めて出直す、ということだと思います。
前回の汗牛足で取り上げた死刑についての議論を少し振り返ると、これは(1)の理念的な議論あるいは(3)の哲学的な議論の要素が強かったと思います。また、前々回の自由意志と刑罰の正当化、という論点から死刑を考えるなら明らかに(3)の議論ですね。一方で(2)の実際的な議論に関して言えば、日本における死刑の実態、凶悪犯罪の実態、犯行から執行に至るまでの一連のプロセスについては、私はほとんど触れていませんでした。しかし今回の汗牛足では、犯行から判決に関する部分にほんの少しですが触れられたと思います。
冤罪について言えば、日本の刑事司法はかなり冤罪を生み出しやすい体質だということが言えるでしょう。それでいて冤罪なら取り返しのつかない死刑制度があるというのはなんとも危なっかしい話ですね。実際、1980年代には死刑判決に対する再審無罪が4件も下されましたし、袴田事件では再審開始が決定して死刑判決から42年(!)経ってようやく釈放されました(2014)。一方で、ついに釈放されず獄死した名張毒ぶどう酒事件(1961)、すでに死刑が執行されてしまった飯塚事件(1992)は冤罪の疑いが極めて強いのですが、いまだに再審が認められていません。(そんなこと認めたら国民に刑事司法不信が広がるのでしたくないのかもね。)実のところ、日本という国は無実の罪で生命を絶たれかねないアブナイ国だった、ということですね!(そんなわけで、「死刑制度は必要」という主張は、「私は冤罪で死刑になってもかまわない」という主張をともなわないなら説得力がないです。)
(2)の議論、つまり日本の死刑の実際について議論するとき、一つ大きな問題があります。それは、死刑の運用に関する情報がほとんど公開されていないということです。死刑囚がどのように暮らしているのかは一般人には分からないし、死刑を執行する絞首台は見学できないし、もちろん執行の場には被害者遺族ですら立ち会えないし、いつ執行するのかをどのように決めているのかもブラックボックス。最大の問題は、情報がない以上実態を把握できない、したがって議論のしようがない、ということです。議論を抹殺する最強の手段は議論の種になる情報を公開しない、ということ。こうすればもはや問題があってもなくても分かりようがないのですから。
***
今年の3月以来、森友問題で公文書改ざんが問題になりましたが、やはり情報管理・情報公開のあり方が一つの大きな問題だと思います。行政部が立法部に対してちゃんと情報公開しないなら問題の存在も所在もゆらいできますし、まともな議論のしようもありません。そんなことでは民主主義は成り立たない。
そもそも信頼できる情報がなければ何の議論も成り立たないわけで、そこを封じられると建設的な議論など夢のまた夢です。だから適切な情報管理・情報公開が健全な民主主義のために本質的に大切なことなんですね。しかし現実には日本はいま明らかに逆の流れに、つまり政府にとって不都合な情報隠し・隠蔽、「秘密保護」の流れになっています。それに加えて思想・良心の自由、言論・出版の自由が、特定秘密保護法、そしてテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)によって明らかに後退しました。こうして議論の土台とも言うべきものが次々と崩れ去って、この日本の政治におよそまともな議論がありえるのか、というところまで来ようとしている気がします。いま日本は末期的症状、あるいはその手前の「小康状態」にある、そう思うのは単に私が青臭いからでしょうか。
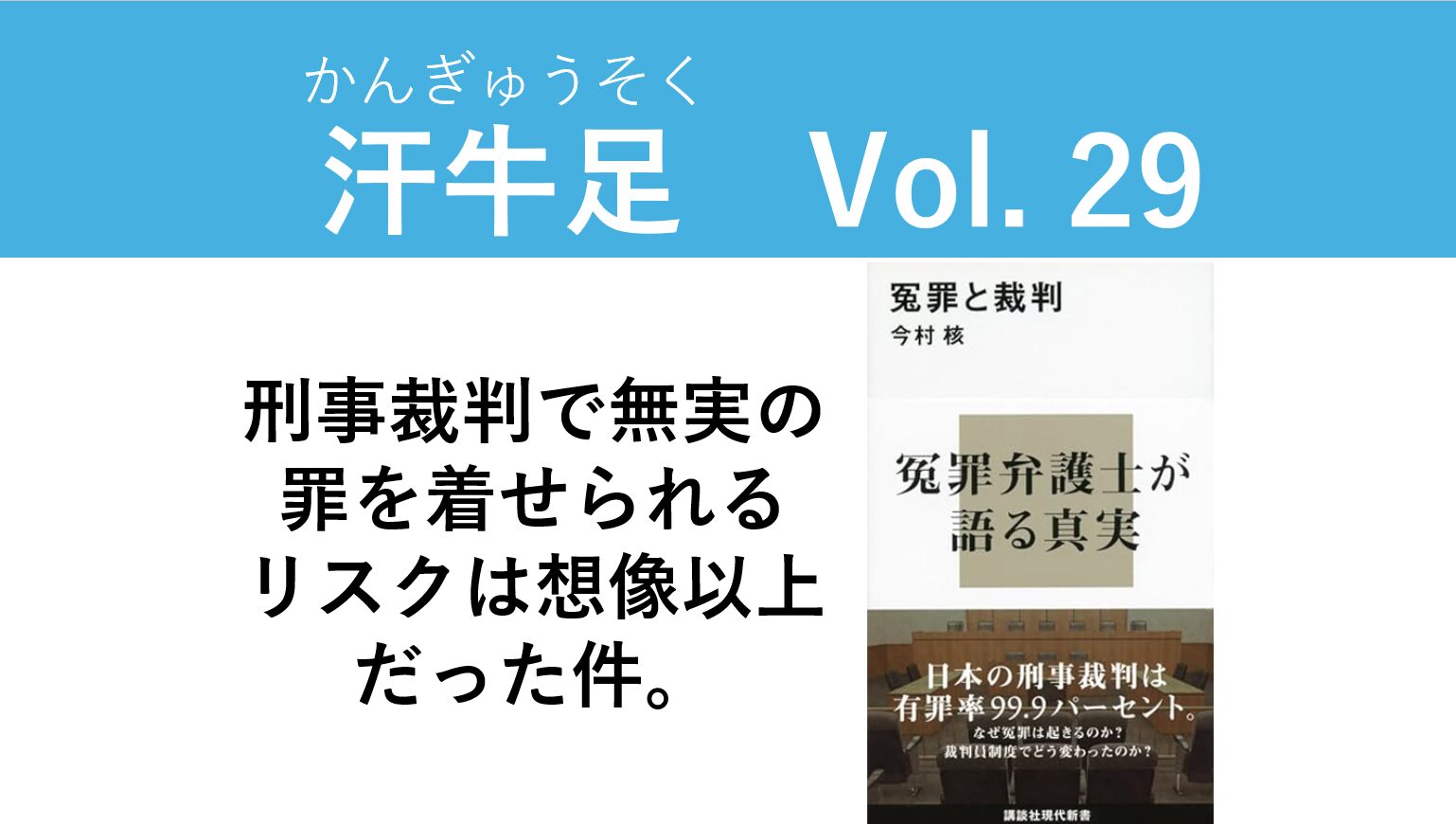


コメント