「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.36 (2018.12.16発行)
◆今回は、前回取り上げた『サピエンス全史』の続きです。サピエンスの歴史の趨勢を決定づけたと著者が言う3つの革命――認知革命、農業革命、科学革命――のうち最後の革命を紹介します。
■ユヴァル・ノア・ハラリ、柴田裕之(訳)(2016)『サピエンス全史:文明の構造と人類の幸福(上・下)』河出書房新社(ヘブライ語版は2011年、英語版は:Yuval Noah Harari (2014), Sapiens: A Brief History of Humankind)
‘Insignificant Animal’ だったホモ・サピエンスは、認知革命によって想像力を手に入れたことで、(遺伝的基盤に基づかずに)柔軟に大勢で協力できるようになり、世界各地に急速に進出し、生態系を一変させました。そして次なる革命、すなわち農業革命によってますますその数を増やし、書記大系と官僚制によって想像上の秩序に基づいた都市や王国を形成するようになりました。また、世界各地に散在していた人間社会がより大きな社会へと統一されていく過程において、貨幣、帝国、宗教という3つの秩序は、特に大きな役割を果たしました。しかしそこから現代に至るためにはさらにもう一つの革命が必要だったようです。それが今回紹介する科学革命 the scientific revolutionです。
科学革命と聞いてあなたは何を思い浮かべますか?コペルニクスの地動説でしょうか、『方法序説』のデカルトでしょうか、「知は力なり」のフランシス・ベーコン?いやいや、やっぱり「プリンピキア」こと『自然哲学の数学的諸原理』を著したニュートンでしょうか。いずれにせよ、17世紀ごろにヨーロッパで始まった近代科学の勃興を思い浮かべる人が大半だと思います。しかしユヴァル・ノア・ハラリの描く「科学革命」はそれとはどうも雰囲気が違うのです。
前回も触れましたが、著者は本書でマクロな視点からヒトの歴史を描いています。したがって、その「科学革命」は一般的な世界史や科学史における科学革命とは当然意味するところが違っています。つまり、ここ500年間の、現在もなお進行中の科学技術の進展とそれに伴う社会の変容を指して、科学革命と呼んでいるのです。(500年以上の「革命」という考え方に違和感を持つ人もいるかもしれませんが、ホモ・サピエンスの誕生が20万年前だとすると、数百年なんて短い期間ですよね。)では、この科学革命期に一体何が起こっているのでしょうか。
著者のハラリが挙げている印象的なデータを紹介しましょう。現在のホモ・サピエンスの生息数は70億匹を超えていますが、1500年には5億匹しかいませんでした。500年で14倍以上になったというわけですね。人類全体の消費エネルギーを見てみると、13兆カロリーから120倍近い1500兆カロリーになりました。そして人類が生み出した財とサービスの総価値に至っては、2500億ドルから60兆ドル、つまり240倍にもなったそうです。
一体何がこのような躍進をもたらしたのでしょうか?ハラリによれば、それは「科学研究→力→資金→科学研究→ ……」というフィードバック・ループによるものだったといいます。つまり、科学研究によって新しい技術がもたらされると、経済成長が促され、そうして得られた資金の一部が再び科学研究に投資され……というループが科学を進歩させ、歴史の流れに新たな勢いをもたらしたというのです。
では、どのようにしてこうしたフィードバック・ループが動き出し、科学革命をもたらしたのでしょうか。この疑問に答えるために、ハラリは近代科学の性質と、ヨーロッパ諸帝国、そして資本主義に着目します。順に見てみることにしましょう。
ハラリは近代科学にはそれまでになかった3つの特質があると言います。一つ目は、「進んで無知を認める意志」です。これは、私たちはすべてを知っているわけではないという前提に立つということと、既に知られている事柄についても異議をさしはさむ余地を認める、ということです。逆に言えば、近代科学の登場以前には、知るべき事柄はすべて知られており、それらは神聖不可侵な絶対的真理とされていたと言います。つまり、神や過去の賢人、聖人はこの世界のすべてを知っており、我々が知るべきことは聖書なりクルアーン(コーラン)なりヴェーダなりに書かれているのであって、そうした聖典や伝統的な知識以外に探究すべき事柄は何もない、と考えられていたのです。
一方の近代科学は、人類は重要な事柄についてすべてを知っているわけではない、という発見、すなわち「無知の革命」によって始まったとハラリは言います。進んで無知を認める意志があるからこそ、近代科学は従来の知識よりも柔軟かつ探求的になったのであり、それが物事の理解や新しい技術の開発を押し進めることになったのです。
近代科学の2つ目の性質は、観察結果を数学的ツールによって包括的な説にまとめることだと言います。従来の知識と観察結果が矛盾した場合には観察結果が優先されることや、数学を援用して法則を記述したことは、それまでの権威ある知識伝統ではほとんど見られなかったことでした。
3つ目は近代科学が有用なツールを提供するようになったということです。それ以前には人々は進歩というものをほとんど信じておらず、人間が実際的な知識を使って問題を解決できるとは考えませんでした。飢饉や疫病、貧困、戦争そして死といったものは超自然的な存在によってもたらされた運命であって、人間がそれらを解決できるという発想は不遜でさえあったのです。しかし、科学がさまざまなツールをもたらし、それまで解決不可能とされていたことが解決されるようになると、人々は科学によって人類の進歩は可能であると考えるようになりました。例えば雷は神の怒りの表われだとされていたものが、ベンジャミン・フランクリンによって単なる電流にすぎないことが示され、避雷針によって回避できるものになりました。それまで解決不能とされていたことは、逃れられない運命などではなく、科学によって解決可能な問題に転化したわけです。
もしもこの3つ目の性質によって科学が有用なツールをもたらさなければ、これほどまでに科学研究が支持され、そこに資金が投じられることはなかったでしょう。科学研究には多額の費用が必要ですが、政府や企業がそのための資金を提供するのは、それがもたらすテクノロジーや応用可能な知識、または彼らにとって都合のいい知見を期待しているからです。もちろん科学者は自身の純粋な知的好奇心に従って研究しているのかもしれませんが、ほとんどの資金提供者はその好奇心を共有していません。彼ら資金を提供するのは、科学研究が自らの政治的、経済的、宗教的な目標のために役立つと考えるからなのです。
したがって、「科学研究→力→資金→科学研究→ ……」というフィードバック・ループを理解するためには、科学研究のみに着目するのではなく、その資金がどのような宗教やイデオロギーの下で投入されたのか、そしてどうやってその資金が湧いて出たのかを知る必要があります。そこで著者が注目したのが、帝国主義と資本主義でした。
著者によると、帝国とは次の2つの特徴をもった政治的秩序だそうです。それは第一に複数の民族を支配していること、第二に国の根本的構造やアイデンティティを変えることなく異国領とその国民を併呑できて、なおかつそうしようとする欲望があったことです。帝国の歴史は古く、現在分かっている限り最古の帝国だという紀元前2250年ごろのアッカド帝国以来、ローマ帝国からオスマン帝国まで、実に数多くの帝国が誕生してきました。
しかし、近代のヨーロッパ帝国主義はそれまでのどの帝国にも見られなかった特徴があったと言います。それは、近代ヨーロッパの場合は科学者のみならず征服者も無知を認めるところから出発したということです。彼らは外の世界がどうなっているか知らないということを認めていたので、新しい領土とともに新しい知識を獲得することを望んでいました。一方それまでの帝国は、この世界をすでに理解していると考えていて、征服事業は富と権力のために行われ、知識は求めていなかったというのです。
ヨーロッパ人が世界について無知であることを自覚したのは、ある大事件が一因になったのかもしれません。それは、1492年にコロンブスによってアメリカ大陸が「発見」されたということです。それ以前はヨーロッパとアジアとアフリカのみが知られており、その他に大陸があるとは絶対的権威である聖書も教皇も知らないことでした。事実、コロンブス自身ですら、自分が上陸したのはインド諸島だと終生信じ込んでいたのです。新大陸の存在を認めるということは、伝統的な知識よりも観察結果を優先するということでもありました。そして何より、自分たちにはまだ知らない重要なことがあるということを認めるということでもあったのです。
新大陸を空白に描いた地図を携えて、ヨーロッパ人はその空白を埋めるべく探検と征服のための遠征を展開します。これはとても異例なことで、なぜならそれまでの帝国は隣国を征服していくことで版図を広げることはあっても、海洋を渡った先の土地まで遠征することなかったからです。ヨーロッパ人にそれができたのはテクノロジーが抜きんでていたからでも資源が豊富だったからでもありませんでした。というのも、当時は中国の明朝が圧倒的な経済力とテクノロジーを誇っていて、ヨーロッパはそれに遠く及ばなかったからです。ヨーロッパにあって中国になかったものは、まったくの未知の土地を知りたい、探検したい、征服したいという、当時としては風変わりな野望でした。
中国もムガル帝国もオスマン帝国も、ヨーロッパの新大陸征服をほとんど意に介しませんでした。彼らは世界はアジアを中心に回っていると信じていて、未知の土地をめぐってヨーロッパと争う気にはならなかったのです。その間にヨーロッパは世界中に基地と植民地のネットワークを構築し、世界初のグローバルな交易ネットワークを編み出しました。そして、アメリカ大陸をはじめ、オセアニア、大西洋、太平洋において圧倒的な支配権を獲得するに至りました。しかし、コロンブスの新大陸「発見」から300年近く経った1775年になっても、世界経済の8割を担っていたのはアジアであって、ヨーロッパの経済力はたかが知れていたのです。
ところが、1750年から1850年にかけて、ヨーロッパは相次ぐ戦争でアジアを打ち負かし、征服するようになりました。そして、こうした帝国事業は科学と分かちがたく結びついていたと著者は言います。例えばイギリスはインドを征服すると、インド全土の測量をしたり、考古学や歴史学、人類学によるインドの歴史や文化を研究したり、インドの生態系を調査したりしました。帝国事業によって新しい知識が次々と獲得されましたし、そうした知識は植民地支配において実用的でもありました。また、このように帝国と科学研究は絶えず新しい知識をもたらしてくれるので、知識の獲得を肯定するヨーロッパ人は帝国事業は進歩的で前向きな事業であると見なしました。新しい知識は進歩を可能にし、被征服民もその恩恵を受けられるのだから、帝国は利他的な事業だと帝国主義者は主張しました。
科学研究はテクノロジーばかりでなく、植民地支配の実用的な知識をもたらし、帝国をイデオロギーの面で正当化するのにも役立ちました。もし科学と帝国が結びついていなければ、1850年ごろにヨーロッパが世界の覇者となることはおそらくなかったでしょうし、科学的知見ももっと限られたものになっていたでしょう。
しかし、著者は帝国の繁栄の要因は科学以外にもあると言います。そこで次に注目するのが資本主義です。
資本主義とは何でしょうか?ハラリによれば、それは宗教の一種です。なぜなら、資本主義は宗教の2つの条件を満たしているからです。その条件の一つ目は、人間には変えることのできない普遍的な秩序、すなわち超人間的秩序の存在を主張するということ。もう一つは、その超人間的秩序に基づいて、人々が守るべき規範や価値観を示すということです。この2つの条件を共に満たすものが宗教で、片方だけ満たしても宗教とは言えません。例えば相対性理論は超人間的秩序を主張しますが、何らかの価値観や人間が守るべき規範を示さないので宗教ではありません。サッカーはさまざまなルールを定め、それを参加者に強制しますが、そのルールは人間が変えることのできないものではなく、国際サッカー連盟が好きにすればよいのです。
資本主義や自由主義、共産主義、国民主義、ナチズムといったものは普通イデオロギーと呼ばれていますが、ハラリの定義に従えば、これらも宗教です。資本主義について言えば、それは経済成長のメカニズム(超人間的秩序)を示し、なおかつ経済成長こそが至高の善である(価値観)と主張します。キーワードはズバリ「経済成長」ですが、これは言い換えると経済のパイが大きくなるということです。
経済のパイが大きくなるという資本主義の信念は近代以前にはほとんど見られないものでした。資本主義以前の社会では、経済のパイの切り分け方にはいろいろあっても、全体の大きさは不変だと思われていたのです。したがって、自分がそのパイを他人よりも多く得ようとすること、つまり大金を稼ぐことは罪悪と見なされました。「金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ易しい」とイエスは説き、金持ちは慈善事業に寄付しなければならなかったのはそれゆえなのです。
経済のパイが不変だと思われている社会では、誰も新規事業で一山当てようと考えなかったようです。むしろ、仮に何かビジネスを始めようと思っても融資を受けるのはほとんど不可能でした。なぜなら、当時の融資は少額で短期かつ高利という条件でしか受けられなかったからです。誰も新しくビジネスを起こさないので、経済は成長しませんでした。経済が成長しないので、新規事業を始めたり、それに融資したりする機運はほとんどありませんでした。つまり、経済のパイは大きくならないという信念は現実のものとなったのです。
この袋小路から脱出するには、科学革命の到来を待たなければなりませんでした。経済のパイは大きくなるという信念を人々が抱くようになったのは、科学と帝国が成功を収めたからです。科学研究は新しいツールをもたらし、それまで解決不能とされていた問題も技術的に解決できるようになると、人々は進歩という考え方を信じるようになっていきます。コロンブスはスペインの投資を受けて新大陸に到達し、結果的にスペインに莫大な富をもたらしました。「投資→植民地→利益→投資→……」というサイクルが回り始めたのです。
近代の経済においては、生産が利益を生み、その利益を生産拡大に再投資すれば、さらなる利益が生まれ……というサイクルによって、経済は成長すると考えられるようになりました。ここで生産に投資されるお金や財や資源は資本capitalと呼ばれ、使われずに蓄えられたり、非生産的な活動に浪費される富wealthとは区別されます。資本主義capitalismは初めは理論として登場し、利益は資本として活用すれば経済は成長すると主張していたのですが、そこに経済成長を最高善とする教義が加わり、近代以降において最も成功した宗教の一つになりました。
帝国と科学はこの資本主義に支えられていたと同時に、資本主義を支えました。帝国事業は経済のパイの拡大に直結していましたし、資本家の利益を守るためなら帝国は戦争も厭いませんでした。科学研究がもたらす発見やテクノロジーもまた、経済成長に大きな貢献をしてきました。
しかし、経済成長を語るためにはもう一つ重要な革命、すなわち産業革命について触れておかなければなりません。また、産業革命のもたらした消費主義と国民主義、そして個人的には本書最大の読みどころである人類の幸福に関する議論も紹介したいのですが、どうやら時間切れのようです。『サピエンス全史』は年内に書き終わろうと思っていたのですが、科学と帝国と資本主義の三位一体についてまとめるのに思いのほか手こずりました。年明けの次回に続きを書く予定です。
◆あとがき
今回紹介したのは全4部あるうちの最後の第4部「科学革命」の約半分です。この第4部は個人的にはもっとも理解しづらかったのですが、今回の執筆を通して内容がようやく分かってきました。読み直していて3つほど発見があったので紹介したいと思います。最大の発見は本書の言う「科学革命」は高校世界史の「科学革命」とは違うということです。高校世界史では科学革命は「17世紀ごろにヨーロッパで始まった近代科学の勃興」という風に説明されますが、私が本書を読む限り、本書の「科学革命」はこれとは全く別物です。すでに書いたように、本書は人類史を俯瞰したときのここ500年の特異さに目を付け、それを「科学革命」と呼んでいます。こう解釈するとそれまでモヤモヤしていたものが氷解しました。なまじ知識があるとそれに引きずられて理解が妨げられることがあると身をもって体感しましたね。
もう一つの発見は翻訳の問題です。例えば上巻10ページの歴史年表には「五〇〇年前」「科学革命が起こる」とあるのですが、これだけ読むと500年前に科学革命が起こった(そして完了した)と誰しも思うのではないでしょうか。しかし原著には年表の500年前の欄に ‘The Scientific Revolution’ とだけ書いてあって「起こる」とは書いていません。確かに原著がミスリーディングだということはできますが。もう一箇所、訳本下巻の133ページには「そこに科学革命が起こり、進歩という考え方が登場した。」という一文があるのですが、原文には ‘Then came the Scientific Revolution and the idea of progress.’ とあります。私なら「そこへ科学革命と進歩という考え方が到来した。」としたいところです。というのも、訳本のように「科学革命が起こり」としてしまうと過去の単発的な事象のような印象を与えかねないからです。「フランス革命は1789年に起こった」なら問題ないと思いますが、科学革命は過去の一時点に突如起こったというわけではなく、500年ほど前から現在まで徐々に続いているものだと解釈する限り、「起こる」という動詞はなじまないように思います。他にも、英語ならではのシャレや、歯切れの良さは訳書では伝わりにくいので、その辺はやはり原著で読む特権だなと思った次第です。
3つ目の発見は、本書の、特に第4部の分かりにくさの秘密です。いや、文章そのものは平易で問題ないですし、個々の話にもついていけるのですが、話のつながりが分かりにくいのです。いろんな話をしてくれるのはいいけど、それとこれと一体どういうつながりがあるのか?というモヤモヤ感が残るままにうまくはぐらかされた印象さえ持ちます。しかし、これはどうも著者の歴史観が根底にあるのではないか、と思うようになりました。著者は歴史を因果関係によって記述しようとしません。なぜなら、歴史の本当の因果関係は知りえないからです。歴史は無数の要因とそれらの相互作用によって展開していくので、条件がほんの少し変わっただけでも結果は全く違ったものになりえます。したがって、歴史について知れば知るほど、なぜ物事が他の方向に進まずこのような道筋をたどったのか説明するのは難しくなると著者は言います。そこで、因果関係に基づく説明を要求する歴史の「なぜwhy」には「わからない」と答え、「どのようにhow」という問いに対しては一連の出来事を言葉で表現して答える、というのが著者のスタンスのようです。今回書いていてやはり著者はこのスタンスを一貫して守っていると感じました。だから「なぜ」に対する答えや「歴史のつながり」のようなものを求めて本書を読むといま一つ分からないまま終わってしまうのですが、「どのように」というのを著者は記述しようとしている、ということ念頭に置けばもっとすんなり読めると思いました。
長い文章を最後まで読んでくれた辛抱強い方に朗報(?)です。本書の内容とほとんど同じ著者の講義の動画を見つけたのでリンクを貼っておきますね。本と内容がほとんど変わらないので、実は本を読まなくてもこれを見ればすっかり分かるという代物です。まあでも英語ですし、とても全部見てられないくらい長いです:
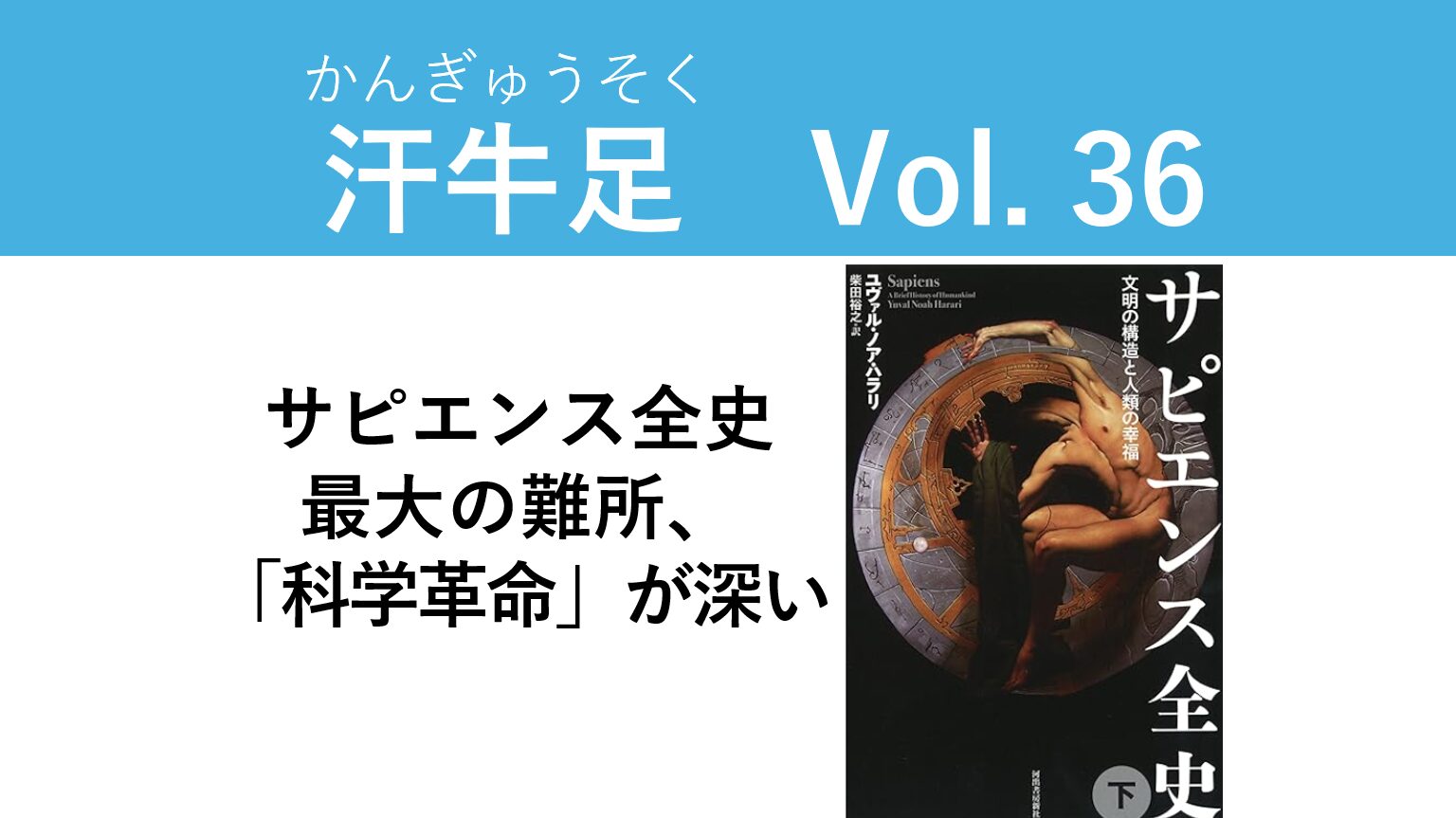


コメント