「汗牛足」はボクが大学生の時に発行していた本の紹介メルマガである。基本的に当時の原文のままなので誤りや内容面で古いところがあるかもしれないが、マジメ系(?)大学生の書き物としてはそれなりに面白いものになっていると思う。これを読んだ人に少しでも本に興味を持ってもらえたら望外の喜びというものだ。
汗牛足(かんぎゅうそく)vol.37 (2019.1.12発行)
◆あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今回も引き続きユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』を取り上げます。科学革命がもたらした変化の後半戦を取り上げたうえで、本書の本丸とも言える、サピエンスの幸福に関する興味深い議論を紹介します。
■ユヴァル・ノア・ハラリ、柴田裕之(訳)(2016)『サピエンス全史:文明の構造と人類の幸福(上・下)』河出書房新社(ヘブライ語版は2011年、英語版は:Yuval Noah Harari (2014), Sapiens: A Brief History of Humankind)
最初に少し前回の話の流れを振り返っておきましょう。人類の歴史を振り返って農業革命以降に注目すると、特にここ500年は明らかにそれまでとは違った傾向を見せ始めました。つまり、ホモ・サピエンスとその家畜たちは猛烈な勢いで増殖し、グローバルなネットワークや科学技術の興隆とともに、将来に対する信頼に裏打ちされた活発な経済活動が見られるようになったのです。そこでここ500年のこうした激変期を指して科学革命と呼びます。前回はこの科学革命の原動力として、科学研究、帝国主義、資本主義が互いに持ちつ持たれつ発展していくさまを紹介しました。そして今回は、この科学革命の中でも一大事件と呼べる産業革命とそれが人間社会にもたらした変化について見てみることにします。
ハラリは産業革命についても人類史を念頭に置いて大きな視点から捉えているようです。彼によると、産業革命はエネルギー変換における革命でした。それ以前のもっとも優れたエネルギー変換装置は人間や家畜の筋肉で、彼らはエサを食べるとその化学エネルギーを利用して田畑を耕すことができました。とはいえ、そのエサは気候条件などの自然環境に大きく左右されていましたし、彼らのエネルギー変換能力も生物学的な限界がありました。ところが産業革命以降になると、大規模で安定したエネルギー変換装置が次々と誕生しました。蒸気機関の誕生に始まり、内燃機関の発明、電気の利用、そして原子力発電や光電池、燃料電池まで、エネルギー利用のあり方は多様化してきました。
莫大で安定したエネルギーが使えるようになると、以前よりも多量かつ多様な原材料を手に入れることができるようにもなりました。例えば鉄の生産性ははるかに向上しましたし、プラスチックやアルミといったそれまで知られていなかった材料や、多種多様な化学物質も生み出されました。
こうした豊富なエネルギーと原材料の組み合わせの登場は、一方で科学研究に支えられていましたが、他方で無限の経済成長を必要とする資本主義経済の原動力にもなりました。このように資本主義が新たなテクノロジーと市場拡大を求めて科学研究に投資し、科学がそれに応えつつ発展する、というサイクルが本格的に回り始めたのは産業革命以降のことです。
また、産業革命は第二次農業革命でもありました。農業は工業化の進展に伴って、その生産性が飛躍的に向上しました。実際に、それまで多くの社会で人口の大半が農民であったのに対し、今日の先進国において第一次産業(農業・林業・漁業など)で生計を立てているのは人口の数パーセントに過ぎません。
(ちなみに著者はヴィーガン(絶対菜食主義者)だそうで、ここで多少脱線して畜産業の工業化によって家畜がどれだけ身体的・感情的苦痛を被るようになったかについて力説しており、これを読むと自分もヴィーガンになりたくなります(なったわけではないです)。家畜の不幸に関する話題は次作の『ホモ・デウス』でも取り上げられているので、また気が向けば紹介します。)
第一次産業に従事する人が少なくなると同時に、第二次産業(工業)、第三次産業(サービス業)が盛んになりました。人類史上初めて、供給が需要を追い越したとハラリは言っています。しかし問題は、資本主義経済が回っていくためにはたゆまぬ生産とともに消費もなされなければならないということです。そこで資本主義と表裏一体の新しい価値体系、すなわち消費主義が登場しました。
消費主義においては、より多くの商品やサービスを消費することが好ましいと見なされます。人々がこの消費主義を実行すれば、生産者も利益を上げてますます生産を拡大させるので、経済成長を至高の善とする資本主義にとってもプラスです。倹約はしばしば美徳と見なされていますが、みんながケチになれば収入も減るので結局経済は停滞せざるを得ません。したがって倹約は悪徳であり、気に入ったものや流行のものをどんどん消費することこそ善行だと消費主義は教えています。つまるところ、資産家などの一部エリート層が投資にいそしんで生産を拡大させる一方で、大衆はそれらをどんどん消費する、というのが資本主義・消費主義の理想であり、実際に今日のほとんどの人はこの宗教の教義を実行しているというのです。
産業革命によって人間が利用できるエネルギーや資源は鰻登りに増加しましたが、一方で地球環境や生態系に甚大な影響も与えています。地球温暖化や海面上昇、環境汚染によってサピエンスの棲みかはより過酷なものに変化しつつあり、自ら招いた災いを乗り越えるために困難な戦いを強いられることになるかもしれません。
産業革命は地球環境を変えつつありますが、その一方で人間社会や、人々の精神構造をも激変させてきました。例えば誰もが正確な時間を気にするようになったことや、都市化が進んだこと、家父長制が崩壊したことなどがありますが、筆者がとりわけ重大なものとして取り上げているのは、家族と地域コミュニティが崩壊し、国家と市場がそれに取って代わったことです。
今日において国家は福祉制度や医療制度、教育制度を提供し、治安を確保し、裁判で争い事を解決してくれます。市場は私たちの生活に欠かせない衣食住だけでなく、保険や情報などのサービスも提供してくれます。しかし産業革命以前において、こうしたものは家族や親密なコミュニティが提供してくれるものでした。人々は互いに知り合いで、お互い支え合いながら生活していました。王国や帝国の支配下にあったとはいえ、コミュニティ内のことはコミュニティで解決するのが当たり前でした。むしろ、伝統的な社会では役人や警察、教師や医師を養えるだけの余剰がなかったので、そうする他ありませんでした。
しかし、産業革命が到来すると、市場はかつてない力を持ち、国家はより多数の役人を動員して統治を行き渡らせようとしました。また、国家と市場は人々に集団の一員としてではなく個人として生きることを可能にしました。それ以前においては、家族やコミュニティから追放されることはほとんど死を意味していたので、人々は自分を殺して集団の一員として振る舞わなければなりませんでした。しかし国家と市場に身をゆだねれば、自分の好きな仕事ができ、自分の好きなところに住み、自分の好きな人と結婚できるようになります。強い国家と市場が強い個人を生み、家族やコミュニティの力を弱めたのです。
ただし、人々は国家や市場からモノやサービスを受けるだけでは物足りませんでした。それまでのコミュニティでの一体感のような、感情面での代替物もまた必要だったとハラリは書いています。そしてその代替物として国家と市場が提供したのが、「想像上のコミュニティ」であり、その代表例が国民nationsと消費者部族consumerです。私が観察するところでは、「日本人」はオリンピックでの「日本の」メダルの数に一喜一憂し、天皇を「日本国の象徴」と見なし、「日本文化」を誇りにしているようですが、こうしたことは人々が「日本人」という想像上のコミュニティに属していると想像しているからこそ可能なのです。一方で消費者部族の例を挙げると、「ベジタリアン」は肉好きより同じベジタリアンに親しみを感じるでしょうし、ひょっとするとMacユーザーとWindowsユーザーの間にも対抗意識があるかもしれません。人間はどうも「ウチ」と「ソト」を分けて、「ソト」には反感を持ったり無関心でいる一方、「ウチ」どうしでは同胞意識を持って団結したり盛り上がったりするのが好きらしく、国民主義nationalismと消費主義consumerismはそのための絶好の機会を与えてくれている、というわけですね。
また、国家と市場の台頭は、特に第二次大戦後の70年間、世界平和をもたらしたと言います。核兵器は人類を滅ぼしかねない大量虐殺の脅威をもたらしましたが、それだけに平和主義が広まりました。国家間の戦争はほとんど現実味がなくなる一方、国家間の交易は盛んになり、経済的な利益を享受できるようになりました。こうして平和からは利益が上がる一方、戦争は損失ばかりで割に合わないものになりました。
ここまで過去500年の科学革命の流れをざっと見てきました。確かにホモ・サピエンスは繁栄し、物質的にはるかに豊かな社会、より安全でより長生きできる社会を作り上げました。しかし、とハラリは問います。「私たちは以前より幸せになっただろうか?」
この問いには2つの極端な回答があります。一つは、人類は歴史を経るにつれて進歩してきたのだから、今の私たちの方が狩猟採集民の祖先よりも幸せであり、未来の世代は私たちよりもっと幸福になるだろう、という進歩主義の立場。もう一つは、狩猟採集民の時代こそ最も幸福な黄金時代であり、農業革命という詐欺にひっかかって以来、人類はますます自らの身体や本来の性向に合わない不自然・不健康な生活を余儀なくされ、真の幸福からは遠ざかるばかりだ、というロマン主義的な立場です。
実は、両者の立場は正反対ではあっても、どちらにも隠れた前提があると言います。それは、幸福は富や健康や身の回りの環境などの物質的な要因によって決定されるという見方です。金持ちは貧乏よりも幸福であり、健康は不健康よりも幸福である、という通俗的な幸福観もまさにその典型なのです。
しかし、幸福とは何よりもまず、本人が幸福だと感じているかどうか(=「主観的幸福subjective well-being」)にかかっているとする見方もあります。たとえ持病を患い貧乏神にとりつかれた人でも、とある健康な億万長者よりも幸福さに包まれて日々を過ごしているということもあるかもしれません。したがって、金を持っているほど、健康なほど幸せだ、というバイアスはいったん退けて、本人が感じている主観的幸福に着目し、一体どのような要因がヒトを幸福に感じさせるのか、を探究してみるのがよさそうです。
ある人がどの程度幸せに感じているかどうかを調べる簡単な方法は、その人にどのくらい幸せか直接尋ねるということです。また、どのような条件によって主観的幸福が向上するかは、多数のサンプルを比較すれば調べられるでしょう。例えば、年収300万円台の人と、1000万円台の人をたくさん集めて、それぞれに自分の幸福度合いを尋ねれば、富と幸福の間の相関関係を調べられます。この方法による調査結果の一例を挙げると、富や健康よりも家族やコミュニティの方が主観的幸福と強い相関関係にあるようです。だとすれば、産業革命以降の物質面での充実は、家族とコミュニティの弱体化ないし崩壊によって、主観的幸福の観点では相殺されてしまったのかもしれません。
しかし、こうした研究における最大の発見は、主観的幸福は富や健康、家族やコミュニティといった客観的な条件のみによって決まるのではなく、そういった客観的条件が本人の期待をどれだけ満たすかによって決まるということだそうです。したがって、あなたがどれだけ客観的に恵まれた境遇にあったとしても、依然として欲求不満に苛まれているならば、足るを知る病床の貧乏人よりも主観的幸福は低くなってしまいます。
幸福が本人の期待によって大きく左右されるものだとすると、マスメディアや広告産業は人々の期待ないし欲望を煽り立てることで、現状への満足から人々を遠ざけているのかもしれません。魅力的な商品の存在を知り、自分よりも恵まれた人がこの世にごまんといると知ってしまった人は、外の世界を知らない秘境の未開人よりも現状に満足するのが容易ではないでしょう。
ここまでは主観的幸福を社会経済的な要因と結びつける心理学的アプローチでしたが、生化学的要因や遺伝学的要因を主観的幸福と結びつける生物学的なアプローチもあります。このアプローチによると、人々を幸せに感じさせるのは宝くじに当たることでも恋人とキスをすることでもなく、体内に快感が生じることにほかなりません。そしてその快感をもたらすのは、神経やニューロンやセロトニンやドーパミンといった、生化学物質からなる複雑なシステムなのです。
主観的幸福をもたらすこの生化学的システムは当然のことながら進化の産物です。そして、幸福や精神的苦痛が進化の過程において果たす役割は、生存と繁殖を促すか、妨げるか、ということにすぎません。もしも永続的な快感を味わう個体がいたら、わざわざ食事や性交をしようと思わないので、子孫を残すことはないでしょう。何をしても快感を得られないという個体もしかりです。一度快感を得てもそれが永続せず、あるいは不快感に取って代わられるからこそ、再び快感を得るために駆り立てられ、結果として生存や生殖の観点で成功することができます。したがって、そもそも人はいつも幸福に感じられるようにはできていないのです。
とはいえ、苦境に陥っても楽天的で、いつも陽気な人もいれば、陰鬱な気分に陥りやすい気質の人もいます。つまり、生化学的システムには個体差があるのです。誰しも気分の浮き沈みはあるとはいえ、感じられる快あるいは不快の強度や頻度には個体差があり、特に何もない時の通常状態の幸福レベルにも個体差があります。したがって、もし社会経済的にどれだけ成功し、円満な家庭を築いたとしても、あなたの生化学的システムそのものは変わらないので、味わうことのできる快不快には依然として限度があるのです。
幸福に関して生物学的アプローチをとるならば、歴史はそれほど重要ではありません。というのも、歴史上の出来事がときに快感・不快感を促す外的な刺激となったとしても、人間の生化学的システムそのものは変化せず、幸福感の程度は私たちと狩猟採集民の祖先とでは大差ないからです。
しかし、生物学的に見た幸福にとって極めて重要な歴史的展開が一つだけあると言います。それは、人間が直接的に自らの生化学システムを操作できるようになったことです。向精神薬はますます広く用いられているそうですし、将来的には脳に直接電気的な刺激を与えることで快感を得たり、ゲノム編集によって持続的かつ強度の快感を得られる人間が誕生したりするかもしれません。
(ハラリが言及しているように、人間が工業生産化され、フリーセックスと合法ドラッグによって誰もが幸福に感じられる社会を舞台としたSFの古典、オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』は、まさに幸福への生物学的アプローチの一つの完成形を示しています。私も昨年読んでみたのですが、1932年に書かれたとは思えないリアルさに大変驚きました。文学的にも哲学的にも興味深い問題作だと思うので、興味のある方はぜひ。)
生物学的アプローチでは、幸せとは快感を経験することに他ならなかったわけですが、こうした見方にはもちろん異論もあります。例えば、幸せかどうかは自分の人生に意味があり、価値があるとみなせるかどうかにかかっている、という見方です。子育てをするほとんどの親は、自分の子どもにどれだけ手がかかり、子育てをしない人よりも苦労を重ねなければならないとしても、わが子こそ自分の幸福の源だと考えています。現世での苦労は死後の永遠の至福につながると信じている人も、自分の人生に満足できるでしょう。自分が有意義な人生を送っているという確信があれば、単調な苦役や逆境も意味のあるものとして受け入れることができるのです。
しかしながら、純粋に科学的な視点から言えば人生には何の意味もありません。ホモ・サピエンスは盲目的な進化の産物に過ぎないからです。したがって、人々が自分の人生に見出す意義は、それがどれだけ有用であろうとも単なる妄想にすぎません。だとすれば、幸福達成のミソはあなたの人生に意義を与える物語を信じ込むことにある、ということになるでしょう。そして幸福の歴史とは人々の心をとらえる妄想の歴史を意味することになります。
ここまでは、いずれも幸福を主観的幸福として捉えてきました。つまり、ある人が幸福であるかどうかは、その人が幸福だと感じているかどうかにかかっているのだから、本人が一番よく知っている、ということです。しかしこれは、自由主義に特有の見方だとハラリは指摘します。自由主義においては、個人の主観的感情こそが最高の権威なので、物事の善悪や美醜、是非はそれぞれの個人がどう感じるかによって決まります。ルソーが説くように、「私が良いと感じるものは良い。私が良くないと感じるものは良くない」のですね。
しかしながら、歴史上の大半の宗教やイデオロギーは、善や美や正義は客観的な尺度によって決まると主張し、個人の主観には重きを置いていませんでした。キリスト教の立場からすると、大多数の人間はヘロイン中毒者と同じ状況にあるそうです。本人が麻薬を注射したときは最高に幸せだと答えても、ヘロインが幸福の源泉だということにはなりません。人間は生まれながらに罪深く、簡単に悪魔に誘惑されるので、弱き個人の感情など当てにならないというわけです。
自由主義と異なる立場をとる宗教や哲学の中でも、著者がとりわけ注目するのが仏教です。仏教によれば、苦しみの根源は束の間の感情を果てしなく追い求めることにあると言います。快感を追求しようとし、不快から逃れようとして、仮に一度それが達成できたとしても、それが永続的に達成されることはありません。私たちの感情は刻一刻と変化するからこそ、特定の感情だけを求めようとあくせくしてもそれは自らを苦痛に追いやることにしかならないのです。
したがって、自分の感情が束の間のものであることを理解し、特定の感情を追い求めることをやめたときに初めて、人々は苦しみから解放されると言います。仏教で瞑想の修練を積むのは、自分の感情が絶え間なく湧いては消えていくのを目の当たりにして、そうした感情を追い求めるのがいかに無意味かを悟り、どんな感情もあるがままに受け入れられるようになるためなのです。
生物学的アプローチも、仏教も、幸福は外部の条件とは無関係であるという点においては一致しています。しかし、生物学的アプローチが内部の快感を追求するのに対して、仏教はそれこそが苦しみの根源であるとし、感情を自分自身と切り離そうとします。現代の資本主義社会と相性が良い(=市場拡大につながる)のは明らかに前者ですが、仏教が教えるように、どれだけ快感を追求しても安寧の境地に至ることはないでしょう。少なくとも、ホモ・サピエンスを改造して持続的な快感が得られるようにするか、ドラッグ漬けにでもしない限りは。
○おわりに
これまで人類は、どれだけ繁栄しようとヒトとして生物学的に定められた限界を突破することはできませんでした。しかし、21世紀においてはいよいよその限界を超えつつあります。地球史上初めて、自然選択を経ることなく、知的設計intelligent designによって生命が誕生しつつあるからです。ハラリは知的設計は次の3つのいずれによっても達成されると言っています。すなわち、生物工学biological engineering、サイボーグ工学cyborgs engineering、非有機的生命工学the engineering of inorganic lifeです。著者は最終章でこれらを簡単に紹介した上で、歴史の次の段階には人間の意識やアイデンティティの根本的な変化も含まれるという可能性について真剣に考える必要があると言います。そう、ハラリの言うように、私たちが自らの欲望を操作できる可能性が開けた今日においては、「私たちは何になりたいのか?(What do we want to become?)」ではなく、「私たちは何を望みたいのか?(What do we want to want?)」という疑問に直面することになるのです。
こうしたサピエンスの今後については、次作『ホモ・デウス』の大きな主題になっているので、次回以降はその紹介ができればと思います。
◆あとがき
最後まで読んでいただきありがとうございます。3回連続で同じ本を取り上げたのは今回が初めてで、毎回長めになってしまったので一体どれくらいの人がついてきてくれたのかは不安ですが、曲がりなりにも最後まで書けてほっとしています。この汗牛足では私が理解したところをできるだけ分かりやすく書いたつもりですが、残念ながら実際の本ほど面白くないことは確かです。ハラリのサイトを見ると本書は世界で1000万部売れたそうですが、やはりそれだけのことはあります。それから、言うまでもないことかもしれませんが、私が書いたものはあくまで『サピエンス全史』の一つの解釈であり、実際に読むのとは全く話が違うということは断っておきます。
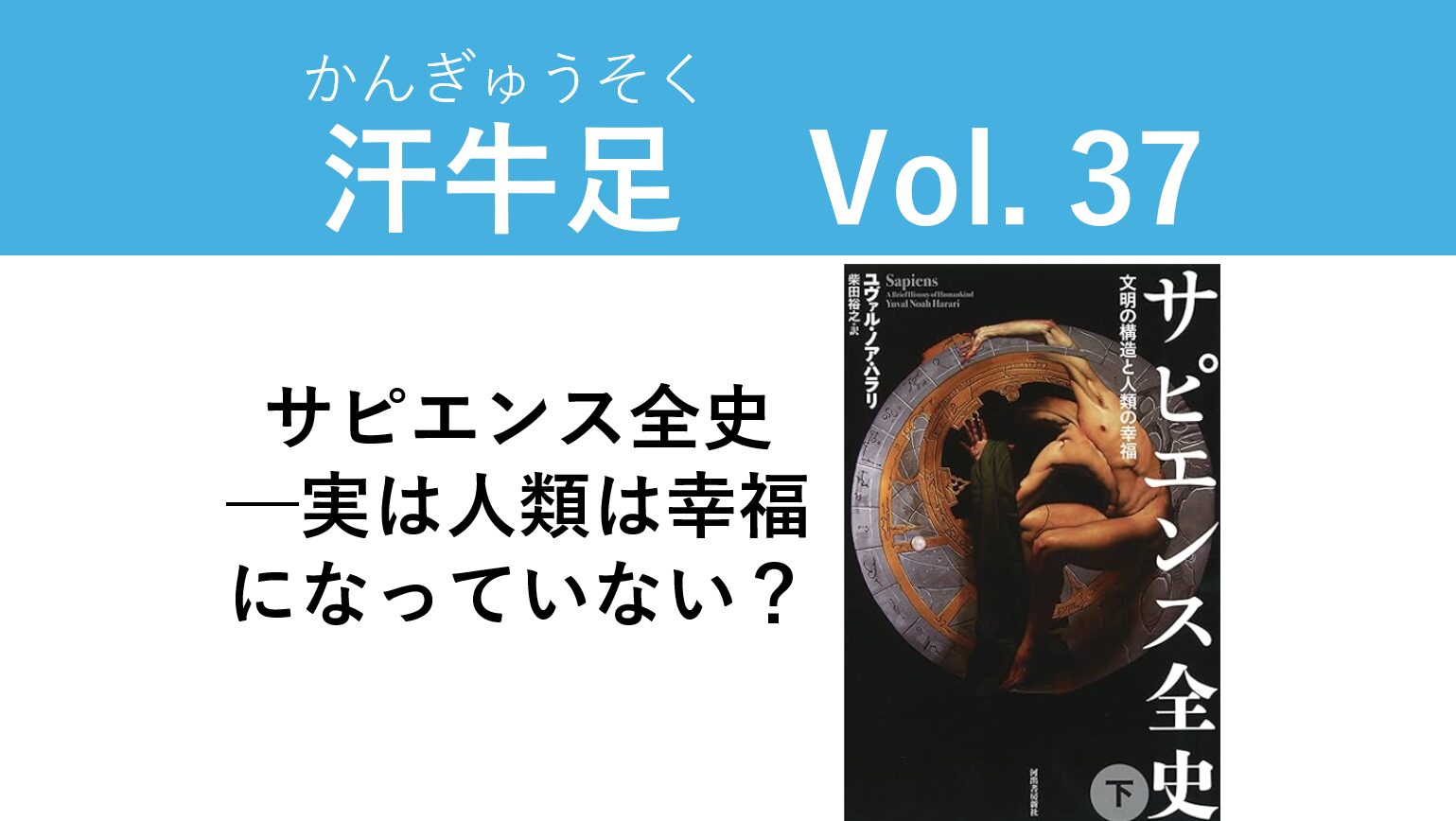


コメント