 読書
読書 三銃士v.s.モンテ・クリスト伯、どちらの方が面白いか?
アレクサンドル・デュマの『三銃士』と『モンテクリスト伯』を読んで。
どちらもアレクサンドル・デュマ(ペール)の有名作ということで、立て続けに読む。三銃士の方は大変面白く、一気に読んでしまったが、モンテ・クリスト伯は長すぎて途中だれてしまった。
イギリスの作家、サマセット・モームは『読書案内』において、三銃士について次のように記している。
 読書
読書  読書
読書 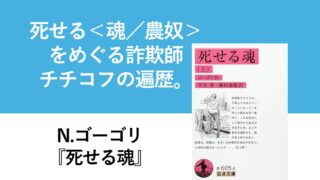 読書
読書  読書
読書  読書
読書  読書
読書  読書
読書 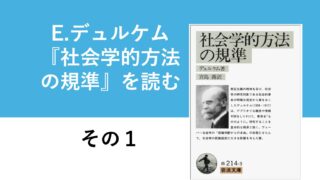 読書
読書 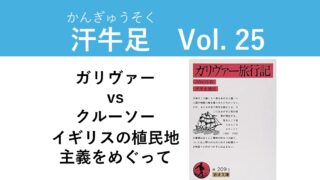 読書
読書  読書
読書